
2007年に結成されたアメリカのポストハードコア・バンド。迸る激情と猛烈なスピード感を持つハードコアで初期は評価を高め、徐々に緩急の精度やスケールを伴ったサウンドにシフト。
その音楽性からDeathwishやEpitaphと契約し、世界的にも人気を得ています。これまでにフルアルバム6作品をリリースし、ここ日本へも2013年、2014年に来日公演を実施。
本記事はこれまでに発表されているフルアルバム6作品について書いています。
アルバム紹介
…To the Beat of a Dead Horse (2009)

1stアルバム。全11曲約18分収録。その収録時間を見ての通りに、2分台が3曲、あとは1分台の曲が並ぶ(#9「Nine」はさらに短くて44秒)。 アルバムの長さや曲の尺は意図的でなく、自然とそうなっただけとのこと(こちらのインタビューによる)。
冒頭こそハンドクラップが意表を突く合図をしますが、そこからは激情という言葉を添えたくなるハードコアの五月雨。作品は、要点を抑えた簡潔さ。余計なことを付け足さないのを徹底しているというか。それでも、短時間に過剰なほどに迸るエナジーが詰め込まれています。
緩急はメリハリ良くコントロールしてますが、前のめりに突っ走ること多し。そして枯れ気味の声で叫び続けるのは若さからではなく、そうしないと伝わらないという想いの表れからでしょう。
初期EPからの再録曲でバンドの魂#2「Honest Sleep」は強烈で、変則的な展開を用いながらも最後は喉と頭の血管が心配になるぐらいに叫んでいる。ライヴにおいて終盤を飾ることが多く、観客と強い一体感を生む楽曲として知られます。
また、ひたすらに走っているだけでなく、#4「Throwing Copper」のようにミドルテンポの重厚なサウンドもあるし、ThursdayのヴォーカリストであるGeoff Ricklyがゲスト参加した#6「History Reshits Itself」はメロディックな光を与えている。
約44秒で駆け抜ける#9「Nine」を終えると、スピードに頼らない方向にシフト。Modern Life is Warのヴォーカリスト・Jeff Eatonが参加した#10「Always Running Never Looking Back」でモダンなハードコアを聴かせ、ラストは”わたしは強い声で生まれたわけではない”と感傷的なサウンドに乗せて叫ぶ#11「Adieux」で締めくくります。
苦悩やロサンゼルスへの思いを吐露したエネルギッシュな作品で、時間は短くてもその情熱にやられます。
なお本作は2019年にリリース10周年を記念し、当時に在籍してなかったリズム隊と共に新たなラインナップで再録。Convegeのカート・バルーがミキシングを担当し、『Dead Horse X』として再リリースされました。
Parting the Sea Between Brightness and Me (2011)

2ndアルバム。全13曲約21分収録。エド・ローズがプロデュースを担当しています。体脂肪率1%ぐらいを目指しているんじゃないかというぐらいにをカットし、2分20秒の#8「Face Ghost」を除くと、全て1分台の曲が並びます。電気ケトルでお湯を沸かしている間に1曲が終わってしまうこともあったり、なかったり。
スピードやメロディを高め、1stアルバムをさらに凝縮したといえる内容です。必要最小限の容量に、最大限を込めることの徹底されているというべきか。
楽曲としてはメロディアスになりましたが、猛烈なペースはなるべく維持して、サウンドは激しいまま。そして切迫感に満ちたヴォーカルと演奏陣のアンサンブルは、感情に強く訴えかける。20分間がまるで弾丸のようです。
#1「~」、#3「’The Great Repetition’」、#12「Home Away From Here」、#13「Amends」など抑えておきたい曲を多数収録。瞬間瞬間で色は随分と変わる。その刹那的な表現、ひたすらに情熱的であろうとする感覚は、Touche Amoreの強み。
シンプルなピアノと悲痛な叫びで綴られる#10「Condolences」という美しい飛躍もある。忙しない中にもメロウさに拍車がかかり、親しみやすさは増しました。ゆえに本作を最初に聴くことをオススメしたくなります。倍速にしなくても短いし。
なお、彼等は2013年1月に初来日。わたしは名古屋公演を拝見しましたが、共に来日したハードコア・バンドのLoma Prietaが荒々しいステージだったのに対し、彼等はもっと一体感を重視したステージ。最後は客席でジェレミーが叫んでいました。
Is Survived By (2013)

3rdアルバム。全12曲約30分収録。前作に引き続いてDeathwishからのリリース。初期のSunny Day Real Estateやスマパンの「Adore」を手掛けたBrad Woodがプロデュースを担当。
冒頭を飾る#1「Just Exit」から待ったなし。加減速自在の展開と迸るエモーションを核にしたサウンドが、大嵐となって吹き荒れます。その鮮烈なギターが鼓膜を突き、力強くぶっ叩かれるドラムが加速させ、青筋を立てながらの必死のスクリームが心を動かしていく。
儚いドラマ性を湛えながら、聴き手を巻き込む熱い喧騒を生み出す#2「To Write Concert」、変幻自在のドラムに支えられて目まぐるしく情熱をぶちまける#4「DNA」などの楽曲のインパクトは非常に大きい。
本作はこれまでのハードコア要素に加え、プロデューサーの影響からかSDREに通ずる90’s Emo風の質感も備えていて、現行のインディロック・シーンとリンクしているような趣もあります。
その中で耳を引くのは清流の如きメロディが行き届いた作りになっていること。ハードコアの体は崩さずに上手くドッキングさせています。
一片の曇りもないリリカルな序盤からエモーションが濁流の様に押し寄せる#6「Harbor」、envyを3分台で凝縮したような静と動の鮮やかなコントラストを描く#10「Non Fiction」といった曲がまた作品を引き立てる。
剛と柔のバランス感覚、そしてゆるやかに沸点に達する曲から瞬間沸騰の衝撃まで構成は非常に練られています。
リズミカルなドラムからシューゲイザー風のアプローチまで懐に収めて決死の覚悟を持って突き進む表題曲#12「Is Survived By」におけるクライマックスがまた素晴らしい。
全12曲で約30分とこれまでのアルバムより10分長いですが、研磨された叙情性があって、さらに幅広いフィールドで支持されるだろう充実の一枚に仕上がっています。
Stage Four (2016)

4thアルバム。全11曲約32分収録。Deathwishからエピタフに移籍しての作品となります。その場にとどまっていてはいけない、というバンドの意志を作品毎に表現の幅を広げて提示。
1st~2ndは完全に短距離専門ランナーという感じのハードコアで、前作となる3rdでは緩急や情緒に広がりのある印象がありました。
それらを経ての本作では聴く側の対象範囲をさらに広げてきています。ヴォーカルのジェレミーは変わらずに叫び続けていますが、ギターがクリーントーンの多用やエフェクトをかけて広がりをもたせている。
極端にアクセルを踏みこんで突っ走る曲はなく、心地よいテンポで駆け抜けていく曲を多めに、全体をメロディアスに補完。言うなれば洗練であり、キャッチーになったというのは感じるところでしょう。
メジャー感のある疾走曲#1「Flowers And You」で幕を開け、3分の中でダイナミックに聴かせる#3「Rapture」、陽性のメロディと中盤でコーラスとのハーモニーを利用した#7「Palm Dreams」などで要所を締め、終盤には哀愁たっぷりの序盤からドラマティックに展開する#10「Water Damage」を配置。
以前ほど速いわけでもないし、激しいわけでもないです。大きなレーベルへ移籍したからの変化というのは当然あるのでしょうが、変わらないことは”エモーショナルであり続けている”こと。そこが全くブレないから音楽性に少し変化があろうと、心を打たれるし熱くさせられるのです。
また本作は、ジェレミーの母が2014年に亡くなったことが大きく影響している模様(タイトルはおそらく癌のステージ分類からきているっぽい)。確かにかつての怒りのエネルギーよりも大らかで包容力があります。
もっといえば人生における喜びや悲しみ、生きることの儚さや尊さが詰め込まれている。Julien Bakerがゲスト参加した#11「Skyscraper」は悲哀の鎮魂歌の如きクライマックスで涙を誘うもの。その一瞬に全てをかけたかのような情熱を目一杯込め、彼等は音楽を鳴らし続けるのです。
Lament (2020)

5thアルバム。全11曲約36分収録。ロス・ロビンソンをプロデュースに迎えて制作。前作に引き続き、Epitaphからのリリースです。
Lament = 嘆き、悲しみという意ですが、本作はその感情は最優先されていません。前作はヴォーカリストのJeremyが母を亡くしたことで自身への処方箋という役割の大きさ。悲しみが根ざしつつも、大らかさとメジャー感が伴う表現の広がりを確実に感じさせるものでした。
本作は、前作から立ち直る/乗り越えてきた果てに完成しています。各インタビューを拝読すると、『Stage Four』リリース後の人生が創作の源泉になっているそう。音楽を通して癒え、音楽を通した人との繋がりの再発見。多彩な表現を用いるようになり、多岐の感情をまとめながら聴く者を鼓舞してくれます。
バンド史上最長となる5分超えの#5「Limelight」は、Manchester Orchestraと共に序盤の沈み込む局面から情熱を大量解放する中盤以降を大きな起伏でもってロマンティックに描き出す。
#8「A Broadcast」においてメロウな立ち振る舞いと牧歌的な要素が絡み、ラストの#11「A Forecast」では叫びのスペシャリストであるジェレミーによる明確な歌とセンチメンタルなピアノが寄り添う。これまで通りじゃいられないという変化の意思が強まっていることを伺わせます。
しかしながら、そういった曲があっても#4「Reminders」が本作の色自体をポジティヴ/陽性という方面に間違いなく振り分けます。メロディックなポップパンクとシンガロンガ必至のサビでどこまでも突き抜ける。
ライヴハウスで肩を組んで大合唱している姿が目に浮かぶ、Touche Amoreの全楽曲の中でも一番に一緒に燃え上がる曲になっています。前作からの希望の先がここ「Reminders」にあったわけです。
フルスロットルの猛烈なオープナー#1「Come Heroine」や表題曲#2「Lament」も独自のエモーションを突き付け、共に前進していくことを約束する。
ほとんどの制作はコロナ禍前とはいえ、疎遠になっていく人と心にこれほどまでに熱情豊かに響く作品もそうはありません。Touche Amoreの音楽は寄り添い、鼓舞し、人々が前進するための力として有効であることを証明しています。
Spiral In A Straight Line(2024)
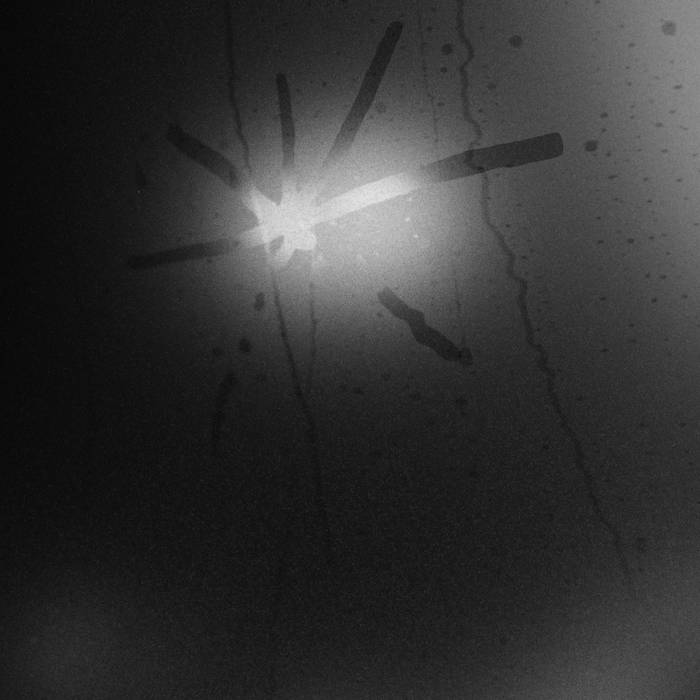
6thアルバム。全11曲約31分収録。レーベルはRiseへ移籍していますが、前作に引き続いてロス・ロビンソンによるプロデュース。これまでプロデューサーやレーベルと2作品続けて仕事し、スパッと切り替えているのですが、これはTouche Amoreの大事な習慣であるとKerrangで語っている。
”親を亡くした悲しみについて歌ったとしても、人間関係における悲しみについて歌ったとしても、それらはすべてつながっているように感じる。私たちが何について書いても、誰かが何か新しいものを感じ取れることが大切だ“とジェレミー・ボルムはROCK SOUNDにコメントを寄せています。
4thアルバム『Stage Four』から続く喪失感は本作にも滲む。しかし#1「Nobody’s」の”だから私たちは前向きに悲しもう“という詞から、人間は抱えながら生きていくものだと主張しているように感じます。
音楽的には前作で感じた陽の気からはあからさまに離れ、シリアスな情緒の方が目立つ。その上で作品を通して激しさと叙情性のバランスを取っています。#2「Disasters」や#5「Mezzanine」における初期の無鉄砲な突撃。これには思わずボルテージが上がるはず。
一方で有名映画監督の名を冠した#3「Hal Ashby」ではメロディアスな進行と口ずさめる歌が待ち構えますが、この曲はこれからアンセムとして君臨しそうな雰囲気があります。
タイトルの”Spiral in a Straight Line”が詞に登場する#6「Altitude」はミドルテンポの中でひりつく感傷が乗っかる。ジェレミー・ボルムは本作時で41歳。年を重ねるにつれて私的な開示や自己批判の精神を歌詞に多く投影し、落ち着いたパートも増えている。だからといって感情や衝動をエコ化してはいません。スポーティな快活さ、フロアを熱狂に包むラインはしっかり維持している。
新鮮な味わいの終盤3曲はこれまでの作品で最もドラマティック。ルー・バーロウご本人登場する#9「Subversion」で枯れた哀愁を表現し、続く#10「The Glue」ではヴォーカル以外は近年のenvyが乗り移ったかのような音像をつむぐ。そして#11「Goodbye For Now」はジュリアン・ベイカーと3度目の共演を果たす終曲で、2人の高め合うようヴォーカルに目頭が熱くなります。ちなみに彼女が参加しないとアルバムは完成しないらしい(いくつかのインタビューで冗談っぽくこの発言をしている)。
”経験していることを書いているからといって、それが何なのか明確にわかっているわけではない。それでも、何年も前に書いた曲から学んでいる“とは再びKerrangより。後退と前進、喪失と獲得を人生では繰り返す。その複雑な感情や思いを吐露する中でもTouche Amoreはハードコアであり続ける。それは本作でも貫かれています。






