
元Nine Days Wonderの川崎氏と清田氏を中心に結成された3人組。ピアノを主体としたジャズ要素が強めのサウンドに、ハードコア由来のドラムを組み合わせているのが特徴。スタイリッシュでいて熱さのある音楽で人気を得ており、TVやCM等に起用された曲も多い。国内外の音楽フェスにも数々参加しています。
“乱暴な言い方ですけど、mouse on the keysのサウンドは、ハードコア・パンクなどに育てられた僕(川崎氏)のドラムに、昔CMや映画なんかで聴いて慣れ親しんだピアノの音がミックスされて出来ていると言えます”(参照:OTOTOYのインタビュー記事より)
本記事は1st~4th EP、1st~4thフルアルバムの8作品について書いています。
作品紹介
sezession(2007)

1st EP。全4曲収録。当時は元NINE DAYS WONDERの川崎氏と清田氏による2人編成。toeのレーベル、Machu Picchuよりリリースされており、サウンド・エンジリアリングに美濃氏(toe)を起用しています。
ピアノとドラムを主体としたスタイルで、そこに電子音やゲスト参加した根本潤氏がサックスを付け加えられるのが特徴。ポストロックとジャズの蜜月関係を築き、芸術性とダイナミズムが連動したサウンドを鳴らします。繰り返しを基調にスリリングに展開していくさまに思わず心が掴まれる。
変拍子を交えた忙しなさとエレガントな美が相乗効果で高め合う代表曲#1「最後の晩餐」はmotkの代表曲(資生堂マキアージュのCMにも起用された)。アンビエントなテイストからフリージャズ風に移行してサックスが自由に踊り狂う#3「RaumKranKheit」、クールでいて疾走感のある#4「a sad little town」も印象的。
16分という短さながらインパクトは大きく、motkのスタート地点にして完成しすぎている。ジャズ出自でないがゆえの反骨精神が反映されているように感じられる点も良いです。なお#2「toccatina」はロシアのピアニストであるニコライ・カプースチンのカバー。
an anxious object(2009)
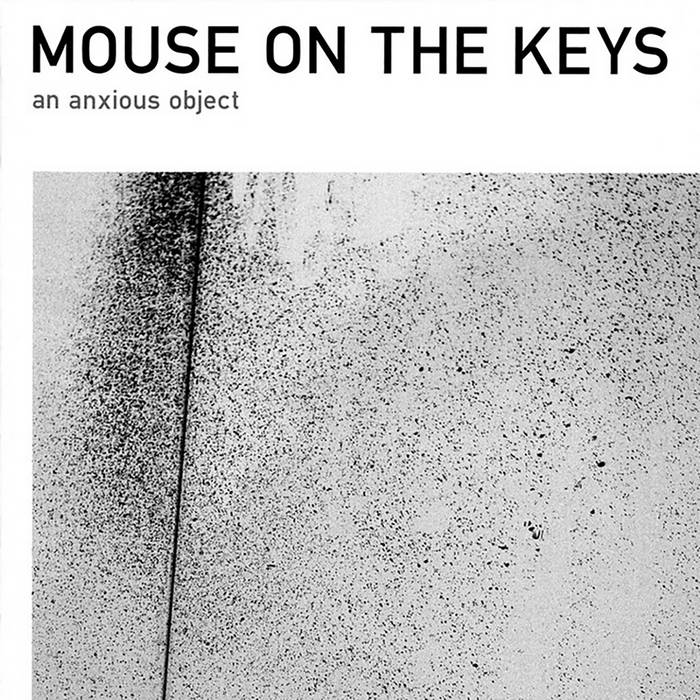
1stアルバム。全9曲約34分収録。新留氏(piano, keyboards)、池田氏(映像関係)を加えた4人編成へ移行。
タイトルは美術評論家のハロルド・ローゼンバーグが述べた”60年代のアートの氾濫に対し、芸術がもはや傑作かゴミなのかわからなくなってしまったこと、そういった作品群をan anxious object(気がかりな物体)と言った”ことからきているそう(CDJournalインタビューより)。
ハードコア由来の焦燥感とジャズの落ち着いた雰囲気。有名小説ではないですが、冷静と情熱の間をスリリングに行き交うスタイルは本作でも発揮されています。そこに混じる管楽器やエレクトロニックのアクセントは前作以上に巧みで、アンサンブルに溶け込んでいる。
ピアノの乱舞に酔いしれるキラーチューン「spector de mouse」、一転して刑事ドラマにも使われそうなイメージが浮かぶ#3「seiren」、終盤にピアノとサックスが情熱をぶつけあう#8「soil」といった楽曲を収録。詩的知的な聴感とリズミカルでパワフルな躍動が融合。motkの特徴はより効力を発揮しています。
なかにはドラムレスで3人ピアノ編成でつくられた#4「dirty realism」もあり。この楽曲は前述のインタビューにおいても”発見だった”という言葉を残し、新境地であることが伺えます。しっかりと手札を増やしている辺りも抜け目がないですね。
machinic phylum(2012)

2nd EP。全4曲約16分収録。池田氏が脱退して3人編成へ。”ヨーロッパツアーやフェスへの出演を重ねることでライヴ・バンド化したこと。それに伴ってみんなで音をいじくりあって曲を作るようになりました(OTOTOYのインタビューより)”と発言していますが、明確に感じるほどの違いはないかなと感じます。
ジャズでありつつハードコアであろうとすると様式はそのままですし、パズルのように音符を的確にはめてスリリングに展開するのも変わらず。
冒頭を飾る#1「aom」も聴いているだけではそう感じませんが、スタジオで録った即興演奏のいいところだけを寄せ集めてイイところだけ切り貼りしてさらにそれを打ち込んだそう(前述OTOTOYより)。
ライヴ・バンド化とは言いますが、流麗なピアノを主体とした中で熱と焦燥がポイントで表出するような形には収めている。スーツを脱ぎ捨ててTシャツ解禁みたいな変化とまではいかないので、その点は安心。上品な鍵盤と荒ぶるドラムの総合芸術と化した#2「Plateau」もそうですが、流動と連動のダイナミクスは相変わらずすごいなと感心。
他にはピアノの音色が波紋のごとき広がりをみせる#4「memory」といった曲を収録。同曲はアンビエント寄りの楽曲ができて新たな発見だったとメンバー自身も手応えを感じている。
the flowers of romance(2015)

2ndアルバム。全10曲約37分収録。”今回のアルバムにはコンセプトはありません“との断言がARBANのインタビューに残ります。
mouse on the keysの音像が共有されているからその必要性がなくなったとのことですが、ピアノとドラムの組み合わせが生み出す、猛々しさと上品さが同居するサウンドはそのまま。#3「Reflexion」や#5「The Lonely Crowd」辺りは、これまで路線を感じる楽曲でしょうか。
その上で音楽的に抑制を効かせており、躍動感は一定レベルをキープしつつ、音響派的なチャレンジングがみえます。#6「mirror of nature」~#8「dance of life」まではその傾向が強く表れているように感じます。滑らかな聴き心地からキュッと外すのが上手いというか。
最後は荘重なストリングスが緊張感をもたらす#9「Flowers of Romance」にシビれ、モーリス・ラヴェル「le gibet」のカバーで不思議な余韻を残して終わる。多彩さと深みの両方を追求した本作には、インスト・バンドとして特異な存在であり続けている表現者の矜持が表れています。
out of body(2017)

3rd EP。全6曲約18分収録。自主レーベルであるfractrecを立ち上げてのリリース。”「Out of Body Experience」で体外離脱、日本だと幽体離脱なんて言われますけど、アルバムのタイトルもそういう意味から取りました“とOTOTOYのインタビューより。
同インタビューでは忙しないものよりはゆったりとしたもの、聴いてて沁みる感じになればなという方向性があったことも述べられます。2ndアルバム『flowers of romance』でも音響派的なアプローチに踏み込んでいましたが、本作ではその延長を掘り下げている。
#2「Earache」のドラムは複雑な動きと躍動感を維持しつつ、茫洋としたエレクトロニックの装飾がミステリアスな雰囲気を拡張しています。逆に#3「Dark Lights」はリズムを抑えつつ、ピアノの優美なフレーズが静かに彩りをもたらしていく。
全体的には陰鬱なタッチが増え、人的な肉体性を控えめ。それによって生ける者の最後の間際だったり、死生観だったりを浮かび上がらせているかのような感触。
#6「Out of Body」なんかはAndy Stott等に影響されたことが感じられるずっしり感がありつつ、空虚さが広がる1曲ですし。厳かなピアノに緊張が強いられ続ける#5「Elegie」はラフマニノフのカバー曲。
tres(2018)

3rdアルバム。全10曲約40分収録。”今回の作品を作る上でひとつあったのが「mouse on the keysなりのエンターテインメントなもの」を作りたかったという感覚があって“という発言がOTOTOYのインタビューに残ります。変化は歌ありの曲が存在することに一番大きく表れているでしょうか。
ここにきて多数のゲストを迎えており、ヴォーカル導入&多彩化作戦を敢行しております。ゲスト陣はアイルランドの男性コーラス・グループのM’ANAM(#1)、カナダ出身の女性シンガー Dominique Fils-Aimé(#3、#6)、私もフジロックで見たChonのギタリストであるMario (#4)、La DisputeのJordan Dreyer(#10)という陣容。
本作でもかつてのようなピアノとドラムのバチバチ感ではない魅せ方を探求しており、じっくりと聴覚に馴染んでくる音運びを重視しています。その最たるものがDominiqueを起用したヴォーカル曲になりますが、冷ややかさの方が目立つmotkの抑制されたサウンドの上に彼女のヴォーカルがソウルフルな温かみをもたらす。
一方でChonのMarioを迎えた#4「Time」ではハードコア/マスロック的な側面をよりオシャレかつ流麗に引き立て合っているのが印象的。それでも一番インパクトがあるのはEPからの再録となる#9「Dark Lights」。ライヴバージョンを基にアップデートされており、尺を7分に引き延ばし、美麗トレモロとピアノの上品なタッチから終盤にサックスが情熱を注入する。この曲はかつてなく轟音ポストロック的。
自身が培ってきた土台を見つめ、新たな要素を加えることでより豊かな土壌を開拓している。その上でバンドのクールで優美なスタイルはそのままに感じるので余計に見事だなと思います。
Arche(2020)

4th EP。全4曲約15分収録。プレスリリースによるとピアノ・インストを全面に打ち出して原点回帰を図った作品だといいます。多数のゲストを交えた3rdアルバム『tres』の広がり。そこを経た本作は確かに前述したコメント通りの作風です。
ジャズ~ミニマルミュージックの気品とエレガンス、そしてポストハードコア由来の忙しないリズムの躍動の融合。一聴してmouse on the keysと言われて浮かぶ音像を体現しており、初期作である『sezession』や『an anxious object』を思わせる雰囲気があったり。#3「Emergence」は特にそう感じさせる曲。
とはいえ、以前よりも体育会系の肉体性は抑えめで、作品を通して流麗なスムーズさの方が勝っている印象です。#1「Praxis」と#2「Room」の硬軟自在に弾かれるピアノの音色と細やかなグルーヴの妙。
ラストにはサックスを引き連れた#4「Anchor」がジェントルな夜を締めくくる。原点への揺り戻しもあれど、より熟成された苦みや甘みが感じさせるEPとなっています。
midnight(2024)

4thアルバム。全11曲約38分収録。6年ぶりのフルアルバムですが、合間にはTBS日曜劇場『ラストマン – 全盲の捜査官 – 』のサントラ、マツモト建築芸術祭での公開制作を基にした『Pointillism』を発表。しかしながら重大なトピックとしてオリジナルメンバーの清田氏(Piano/Keyboard)が2021年に脱退し、翌2022年に白枝氏(Piano/Keyboard)が新加入しています。
その影響か、はたまたmidnightというタイトルからなのか。抑制されたトーンでつづられた作品というのが第一印象。ハードコア由来のドラムがよりミニマルなスタイルへ寄せ、ピアノも厳かなタッチでモノトーンの領域に沈んでいく。あえてだとは思いますが、人間的な感情や熱を制御して無機質さが目立つつくり。
#4「24:59」と#5「Two Five」には北ロンドンのエレクトロニック系ミュージシャンであるロレイン・ジェイムスが参加してますが、しめっぽく漂う歌声を夜の帳に重ねている。でも主役という働きはしていない。
前作がバンドの多芸化促進と間口の拡大を担っていました。それに対して本作ではミニマルミュージック色が強く、ゲストも含めた全員が黒子役に徹しているかのよう。楽曲ごとに夜の濃紺をグラデーションで表現している、そんな感覚が強いです。
特に印象的なのは表題曲#6「midnight」。徳澤青弦氏や元envyの飛田氏が参加したアブストラクトな揺らぎの中で、官能的な色合いが漏れてくる。








