
2024年版に続き、2025年も継続して同内容のものを新たに定期更新していきます。2025年版は読んだ本一覧とし、基本的には読了したものを全部載せていきます。近い内容のことはX(旧Twitter)に書いたりしますが、ここでしか書かないこともあるので、お時間あるときにお読みいただければ幸いです。
”読書のお供に”なんて言うつもりもありません。こういった本を読んでるんだと知っていただければ十分です。
2025年読んだ本一覧①
森博嗣『日常のフローチャート』
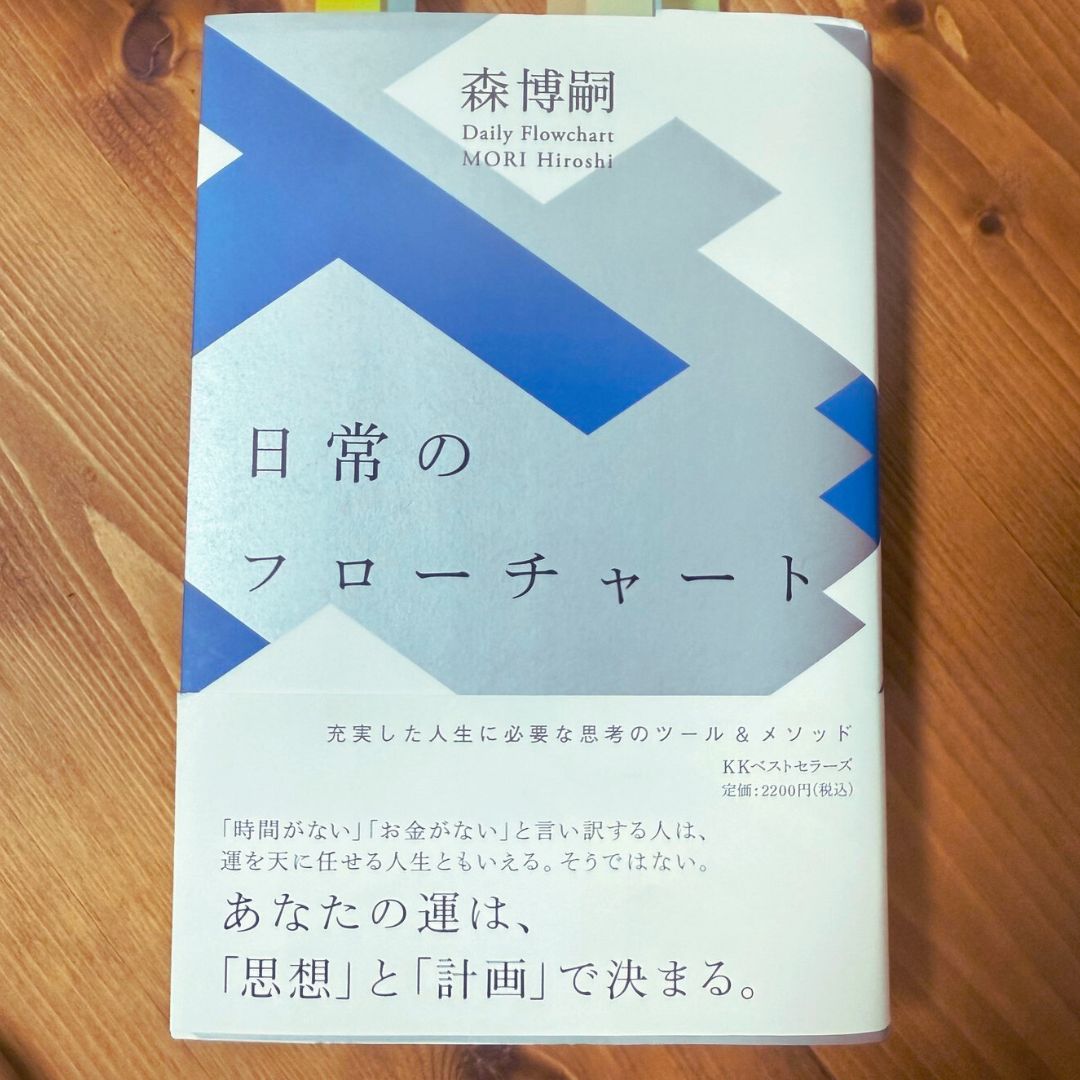
考え方は年齢を重ねるにしたがって変化する(p70)ともありますが、同じになりたい症候群とか、自分と違う人を尊重するのが優しさとか森博嗣節を淡々と述べているのは相変わらず。
”自分の生き方であっても、人は宇宙の中にあり、自然の中にあり、社会の中にある(p89)”という点は常に意識しておくべきことでしょう。孤独を愛そうと、人間という枠組みや共同体からは逃れられない。あと、森博嗣はFIREしているという言説を真っ向から否定していたのは笑いました。
もし、できたら損をしたくない、できるだけ搾取されたくない、という思いがあるのなら、並んだ商品から選ぶだけの人生に、行列に並ぶだけの人生に、ときどき抵抗することである。自由とは、選ぶものではない、並ぶことでもない。作るものだからである
『日常のフローチャート』p273より
人生を充実させるために最低限必要なものとは、思想と計画である。そして、補助的に必要なものとして、時間、資金、場所、他者、才能、努力、運、などがある。「時間がない」「お金がない」と言い訳する人は、思想と計画を持っていない。運を天に任せる人生ともいえる。 そうではない。あなたの運は、あなたに任されているのだ。
『日常のフローチャート』p290より
ジェーン・スー『介護未満の父に起きたこと』
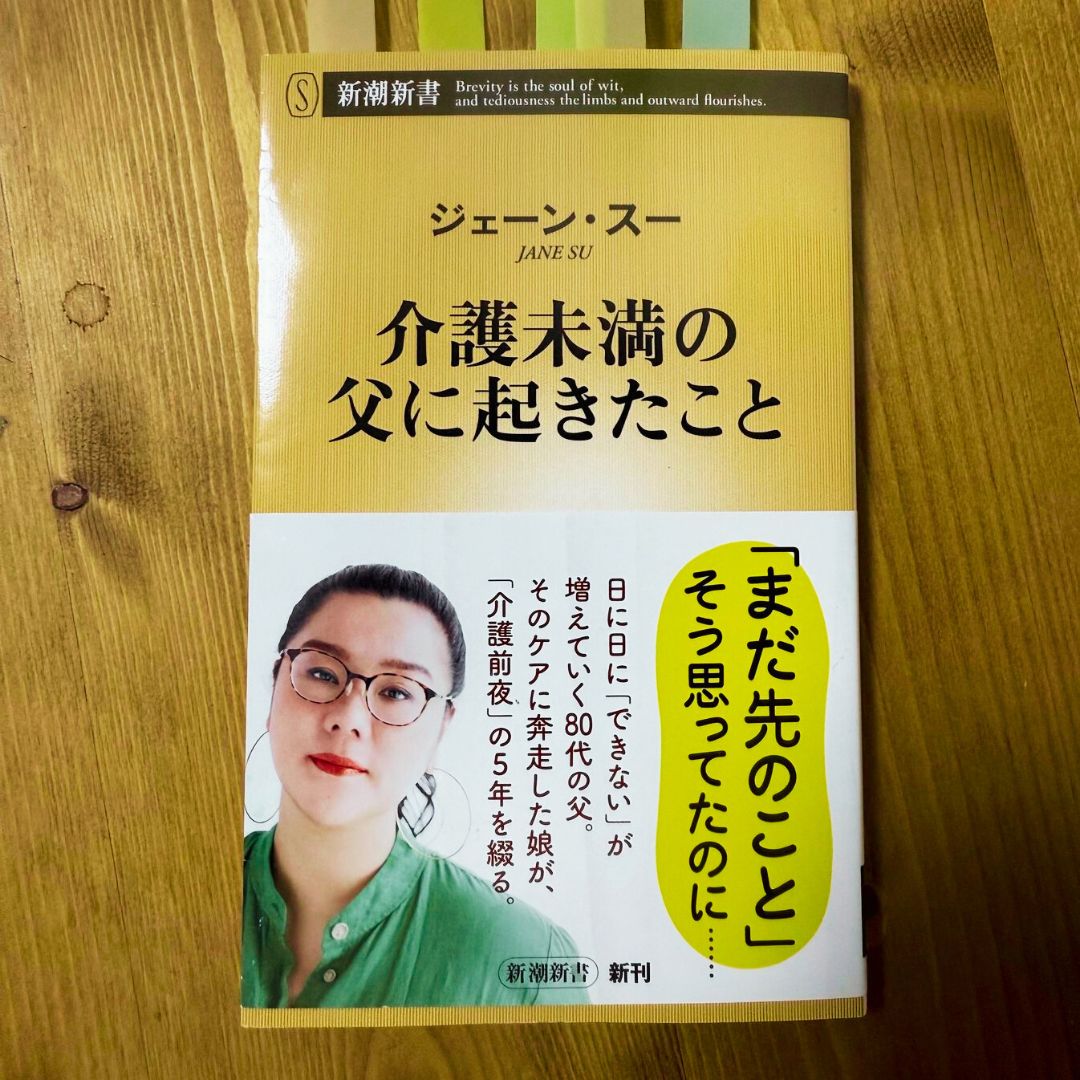
”父のケアは終わらないフジロックフェスティバルだと思うことにした(p49)”を始め、軽妙な語り口でつづられる著者の父へのケア日記。ビジネスライクに、適切な距離感で問題解決にあたる。おそらくほとんどの人が避けて通れない未来にあるだろう問題への予習として、読んどいてよかった本です。
老人は子どもと違い、生きているだけでできることが増えるわけではないのだと痛感する。後退するスピードを、どこまで遅らせられるかでしかない。その中で介護される側もする側も、どれだけ機嫌よく過ごせるかが鍵なのだろう
『介護未満の父に起きたこと』p152より
嵐の夜を何度も越えて辿り着いた答えはやはり、「父と私は別人格だから」だった。どちらが正しいという話ではないのだ。正しさを求めると、必ずどちらかが傷つくことになる。心が傷つくと、ケアはできない。されるほうも、心身共に弱ってしまう。人格が別なのだから、考え方も欲しい成果も異なる。こればかりは致し方ない。そして、これは父の人生である。どこまでいっても、主人公は父なのだ
『介護未満の父に起きたこと』p218より
山田尚志『きみに冷笑は似合わない。』
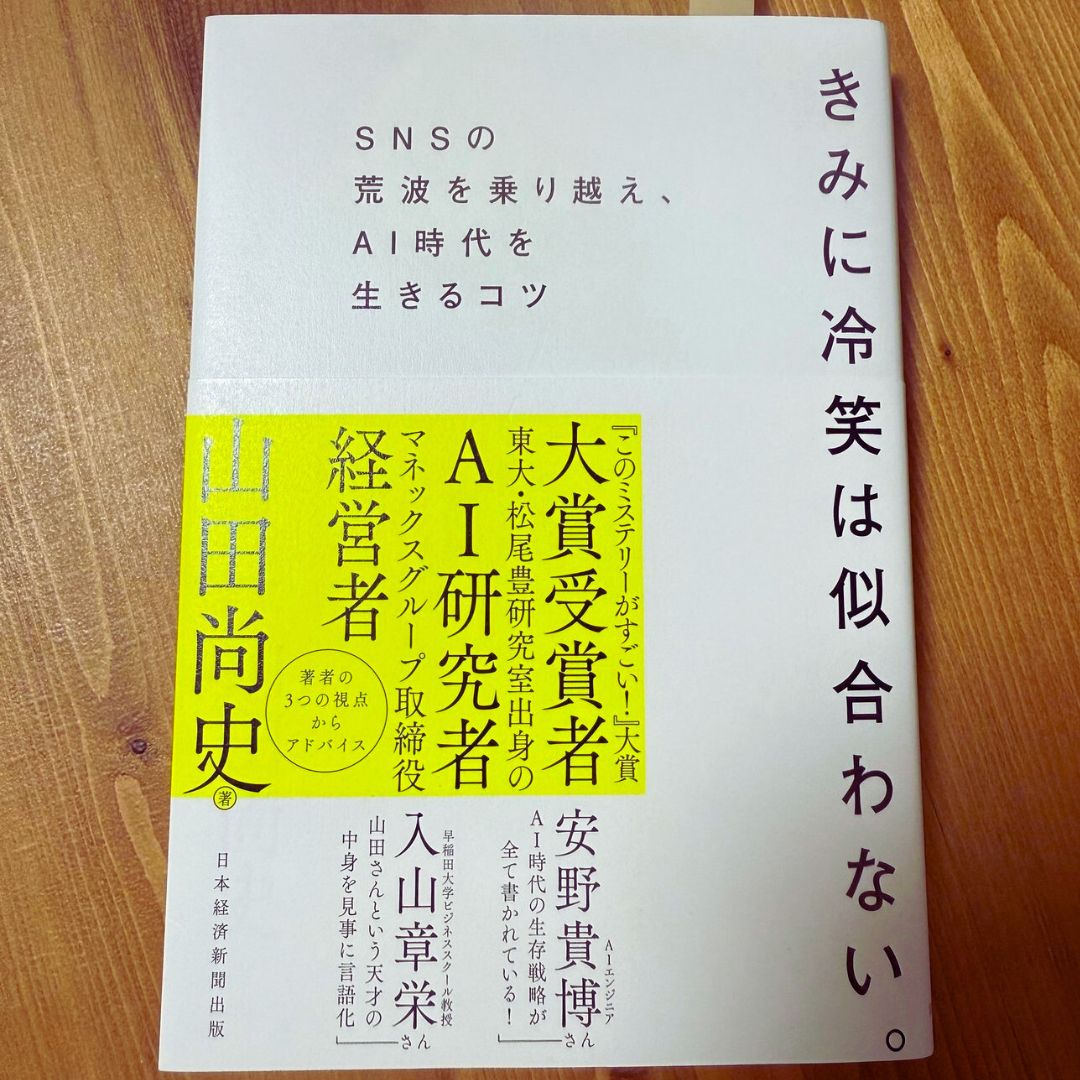
自分の人生において、SNSがどれだけの地位を占めるかは、自分で決められるはずだ。リアルな生活を犠牲にして、そこに全力を注ぐ人がいたってもちろんいいのだが、もし息抜きとして触れていたはずのSNSで、「自分も有名になりたい」 「なんで私は注目されないんだ」「成功者がねたましい」といったような焦りや負の感情が湧いてくるようであれば、一度距離を置いて、自分にとって何が大切かをゆっくり考えた方がいいだろう。
『きみに冷笑は似合わない』p126より
人から聞いた言葉で非常に印象的だったのが、「個性とは、世界の平均からの差分である」というものだ。あなたは世界の平均だろうか。そんなはずはない。だとすれば、その平均からのずれが、あなたの個性ということになる。そして、平均からのずれは、訓練によって大きくなることもあり、何かで卓越するにあたっては、粘り強い努力が必要不可欠である。
『きみに冷笑は似合わない』p191より
横山勲『過疎ビジネス』
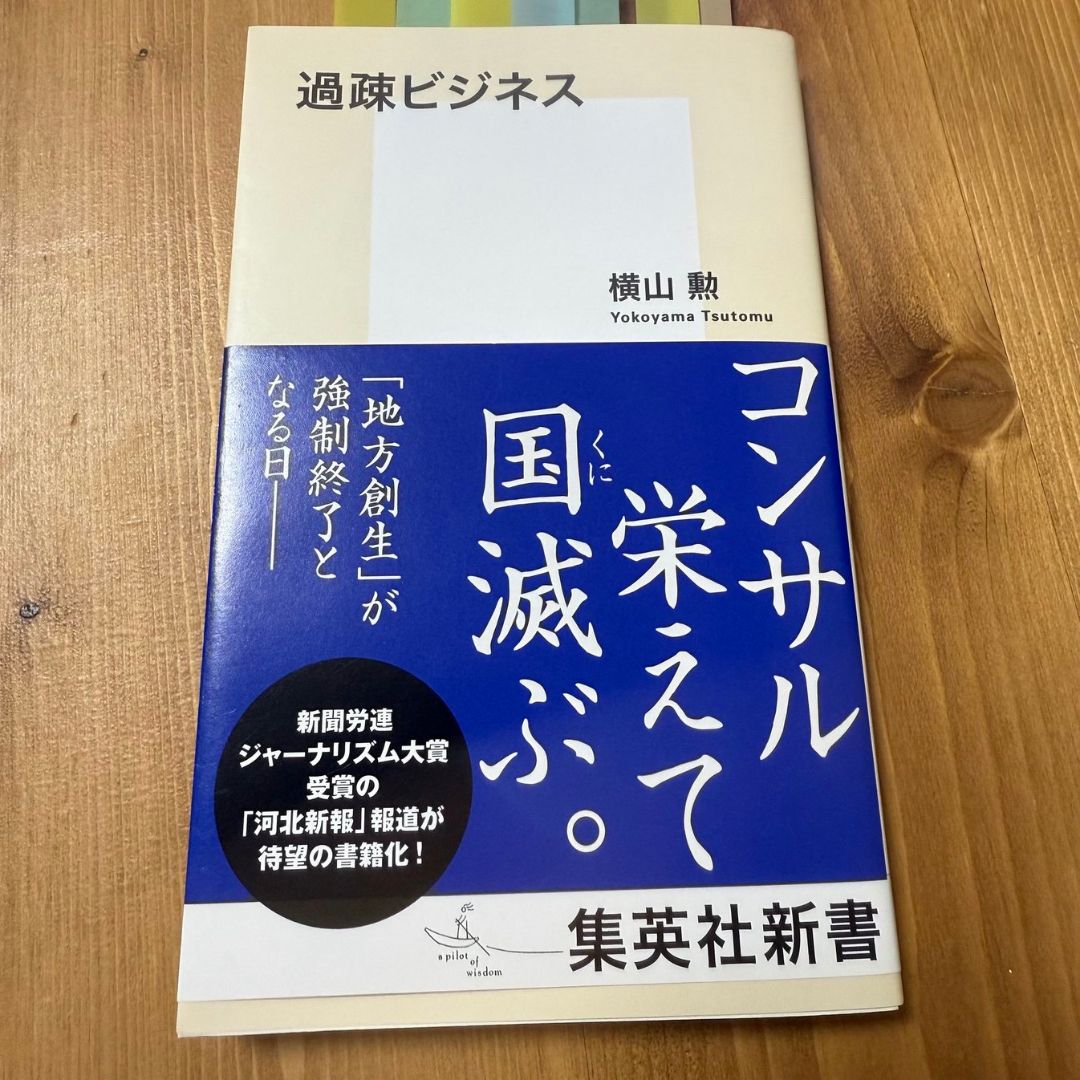
コンサル栄えて国、滅ぶの帯にある通りの内容。過疎にあえぐ自治体に近づき、公金を食い物にする「過疎ビジネス」の実態が丁寧な取材のもと書かれている。福島県国見町での出来事を中心としていますが、どこも他人事ではない。
「地方議員は雑魚だから。無視されるちっちゃい自治体がいいんですよ」とかよくわかんねえコンサルがよく言えるな。逆にすごいよ。まあ、この発言がいろいろな引き金になっちゃうんですけど。マイナス面ばかりの本書ですが、地方創生の成功事例として岩手県紫波町の「オガールプロジェクト」を取り上げており、できるかぎり内製化していくのは大事なことか。
この先の地方は人口減少に拍車がかかり、否応なく過疎化が進む。過疎自治体は国から投じられた補助金や交付金で延命を続ける。そこに目をつけた都会のコンサル企業が言葉巧みに群がってくる。官民連携の名の下に行政機能の外部委託が進められ、地域は自ら考えることを止める。やがて自治体行政はコンプライアンス意識が根本から崩壊した「限界役場」と化す。そんな地方創生が死ぬ日が来ないことを願う
『過疎ビジネス』p269
マッテオ・B・ビアンキ『遺された者たちへ』
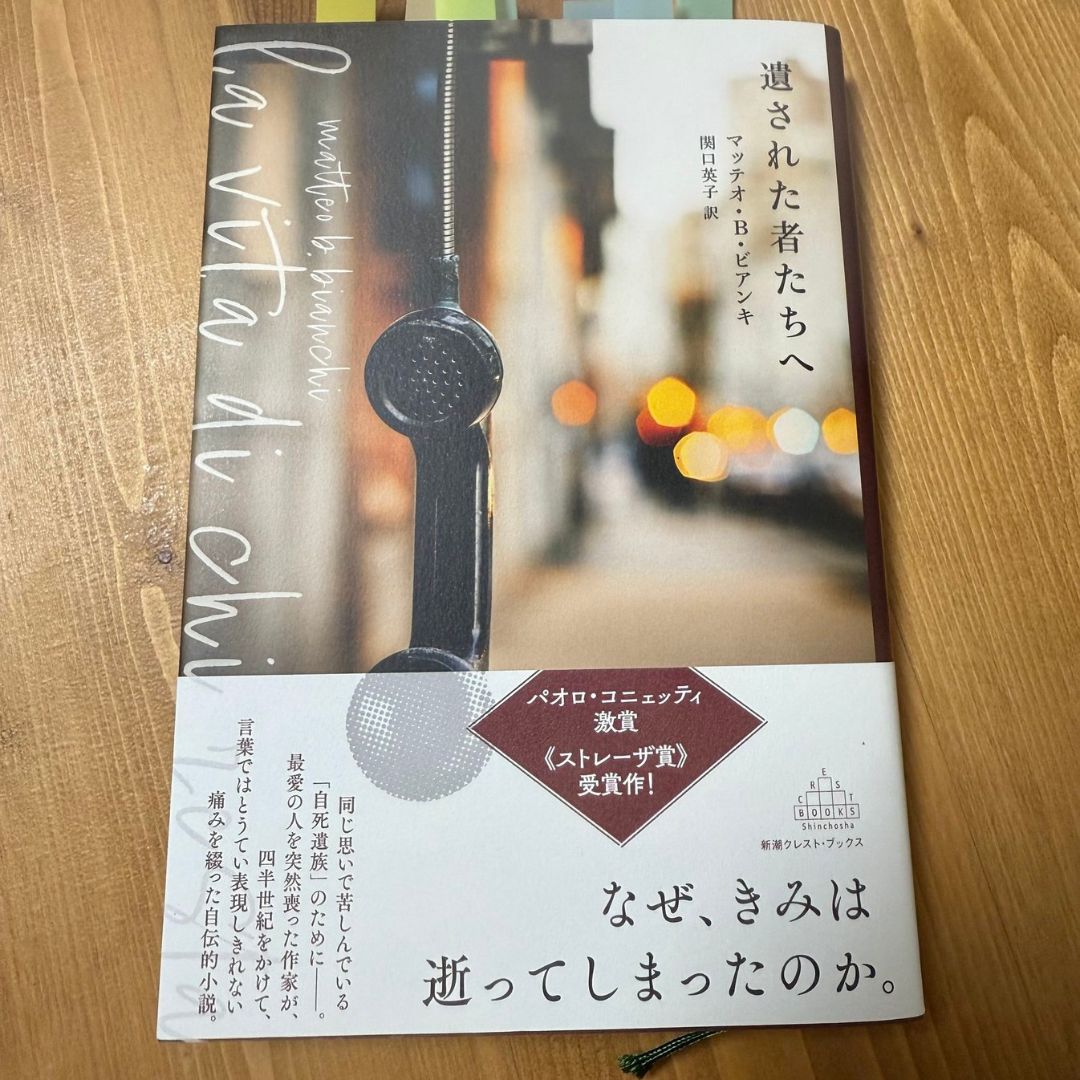
1998年のある日。7年間同棲した後に別れたパートナーが自死。その実体験を基にした自伝的小説。20数年かけて刊行されていることからも、苦しみや喪失からの再生は時間を要する。著者曰く「小説という形をした喪の旅」と表現した本書は、静かに胸を打つ。
苦しみの隣には、つねに現実世界から乖離したような感覚がある。あたかも自分と現実世界のあいだにガラスが存在するかのように。薄いけれども実体を伴った隔たりがあり、それが僕を傍観者とするのだ。 まるで自分は恒久的に別の場所にいるかのように。 そこは以前には一度も足を踏み入れたことのなかった場所で、ひどく個人的な、到達不能な深淵なのだ。純粋な苦しみには、一種独特の驕慢が宿っている。
『遺された者たちへ』p78より
鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』
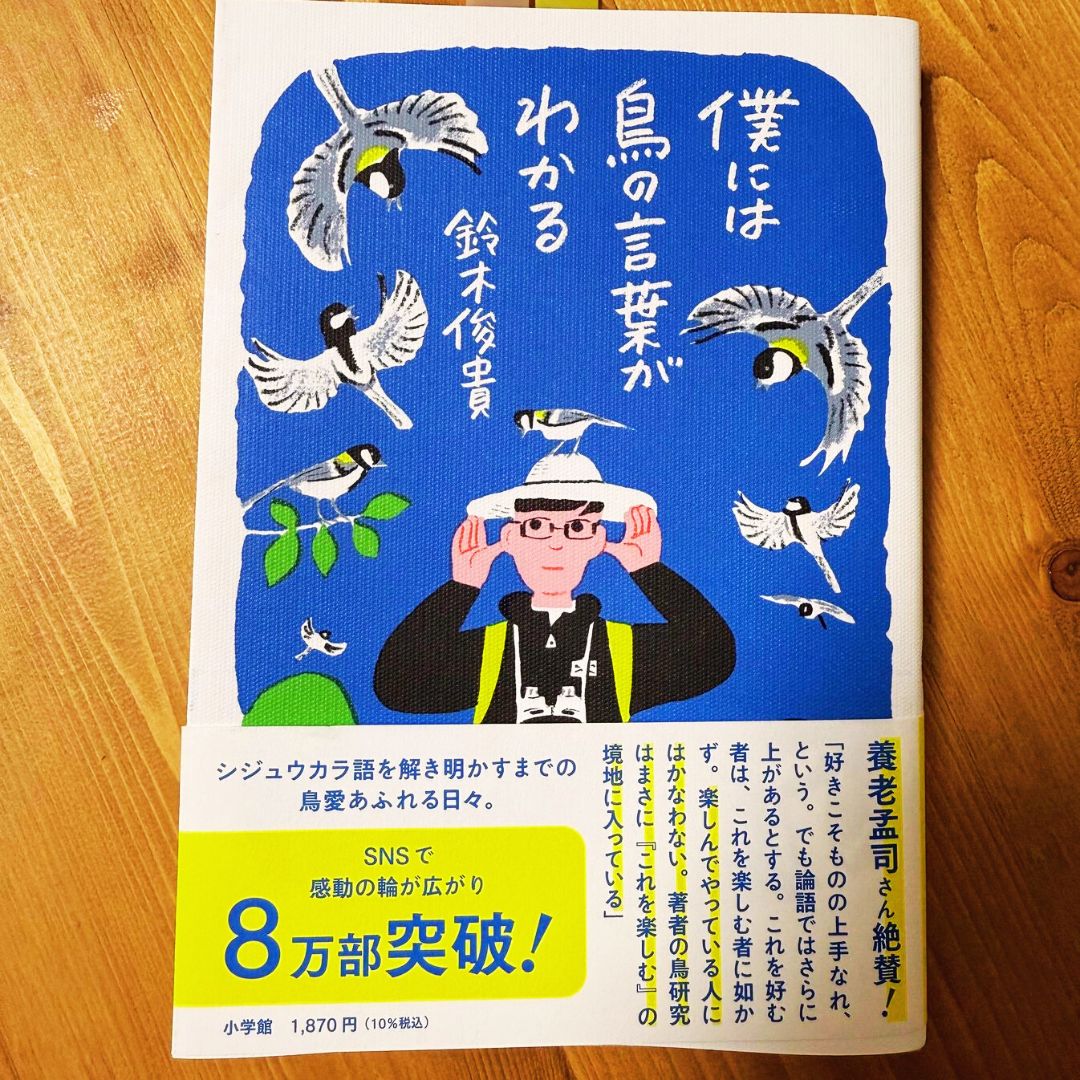
鳥には鳥の言葉がある。動物言語学者による研究エッセイ。ですが、お堅い内容ではなく。これを読んだらふとした時に見つけた鳥がどんな鳴き声なのか気になってしまう。そんな著者の語り口や熱意がとにかく良いです。鳥の言葉を証明するために、楽しみを忘れずに観察し続けるすごさ。
しかし、いつしか人間は自らの持つ「言葉」によって自然と人間を切り分けていった。「動物には言葉がない」、「人間が最も高度な動物だ」、「人間は自然を支配する特別な存在だ」と言葉を並べ、そう思い込んできたのである。そして、とうとう動物たちの言葉を理解できなくなってしまった。それどころか、自然とのかかわり方も、共生から利用へと変わってしまったのだ。今日解決されていない諸々の環境問題も、こうした井の中の蛙と化した人間たちの暴走によるところが大きいと、僕は思う。このままでは、そう遠くない未来、人類も地球も滅びるだろう。
『僕には鳥の言葉がわかる』p234より
宇都宮直子氏『渇愛』
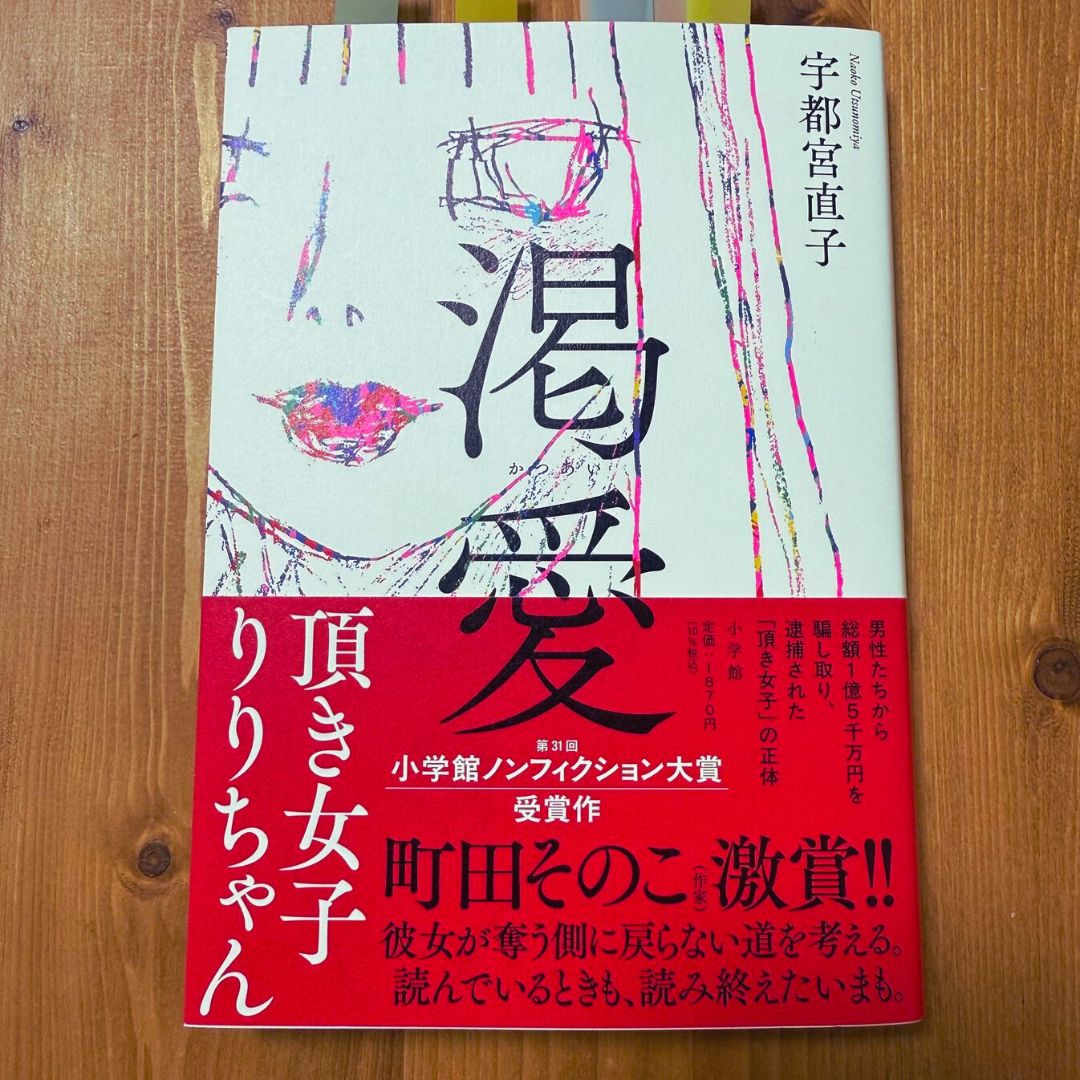
被告人は現代社会がつくってしまった的な擁護ムーブに終始する本かと思ったら、中立的な立場で書かれた読み応えあるノンフィクションでした。
著者が被告人と24回にわたって面会し、対話を続けたこと。被害者の沈痛な思いを始め、被告人の支援者、そして被告人の母からの言葉。こうした丹念な積み重ねを通して事件の背景や人物像が浮かび上がってくる。最終的に著者の思いは、被告人が罪を理解し、償っていくことですが、それがよもやこんなに遠いとであるとは。
映画化の話はなくなったようですが、その際に監督を引き受けていた小林氏の「これは男女の問題ではない。弱い立場にある、困難を抱えている人を型にはめる方法を流布したのであれば、悪だと私は考えます(p229)」という言葉が印象に残る。
田中慎弥『孤独に生きよ ~逃げるが勝ちの思考~ 増補改訂版・孤独論』
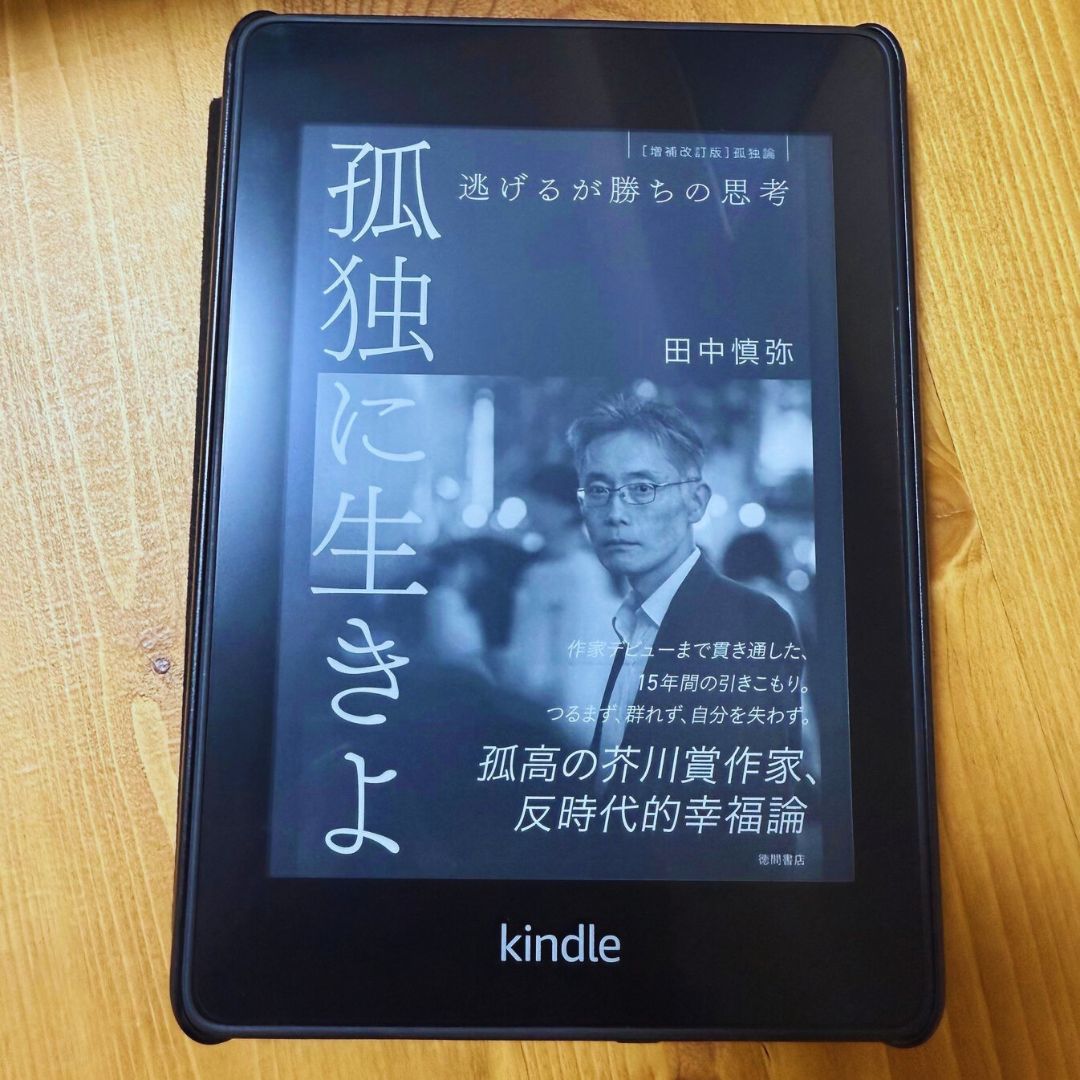
15年の引きこもり経験がある芥川賞作家・田中慎弥氏。著者の小説は『完全犯罪の恋』だけ読んでます。本書で一貫した孤独の状況に身を置いてこそ力を出せる/活路が見出せるみたいな著者の言説。それは私も同じように感じるから理解できる部分です。
しかしながら、氏のようにインターネットを隔絶し、パソコンやスマホの電子機器は所有すらしておらず、今でも原稿は手書きという極端さには至っていない。RehacQの動画だとそういった極端な状態にしないと、他の才能豊かな書き手には勝てないと仰ってましたが、書いて生きて行くためにそこまでする。これぞ狂気だなと。
本を読め。本を一冊読んでいる間は生きていられるという言葉もまた印象的。それに古典を読んだ方が良いというのは近藤康太郎氏にも通ずる。オススメの一冊です。
みずから積極的に手を伸ばしてつかんだ言葉でなければ、充分な用をなしません。 日々意識しないと、言葉は本当に目減りして、やがて枯渇してしまうのです。 するとどうなるか。言葉はわたしたちの考える素です。行動を決めるのも言葉です。 枯渇すれば、能動的に活動することがままならなくなる。 何度も述べてきたように、それは思考停止を意味する状態であってあなたは望まない環境に閉じ込められても、それに抗えない奴隷となります。 言葉は本来の自分を保つための武器なのですから、ゆめゆめ疎かにしてはいけません。
『孤独に生きよ ~逃げるが勝ちの思考~ 増補改訂版・孤独論』より引用
ReHacQに出演された時の動画がおもしろいですよ。前後編ともに45分ありますが、作家論にしろ人生観にしろ良い。孤独だけど、人間ひとりじゃ生きられないともはっきり言っている。
佐々木敦『書くことの哲学』
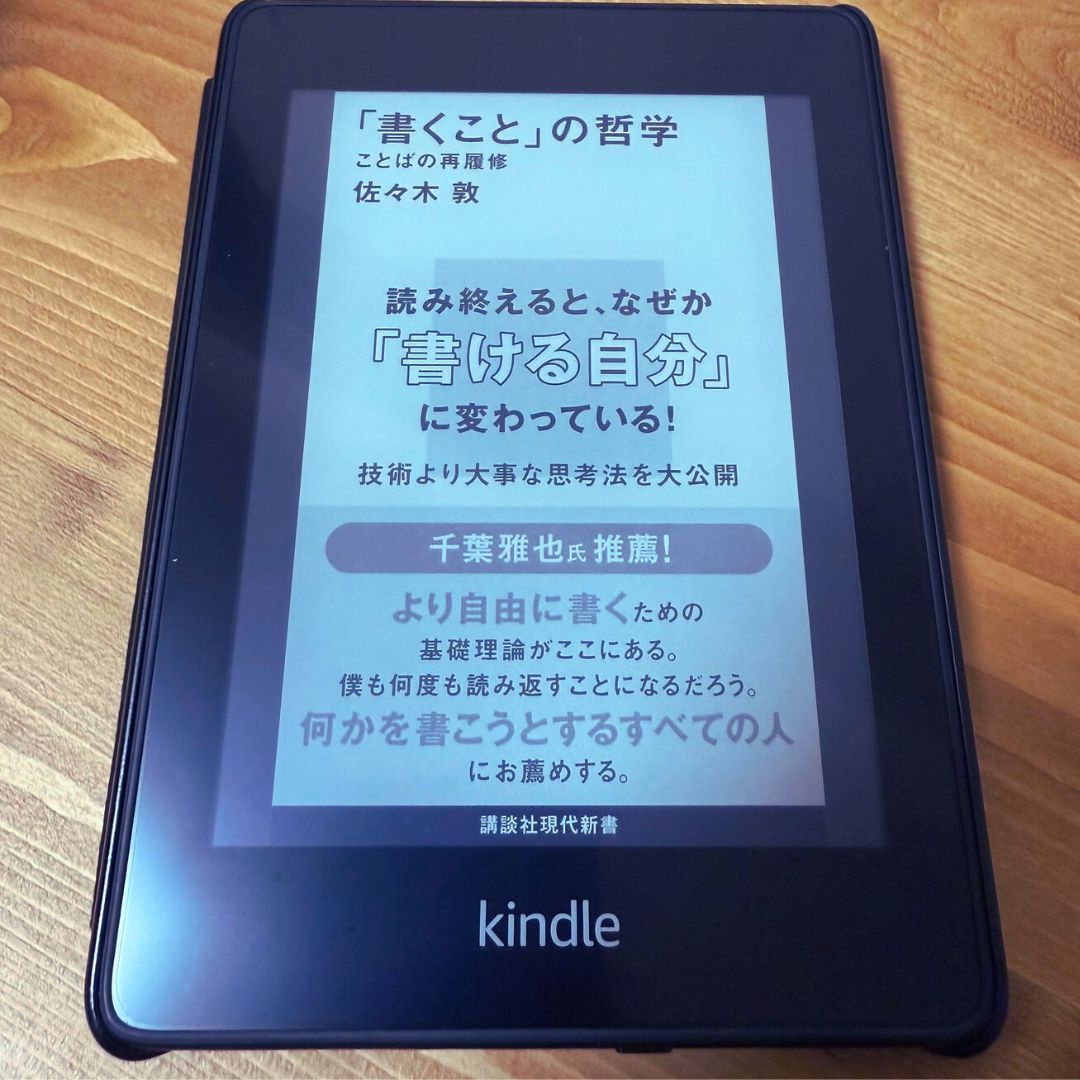
帯にある”書ける自分に変わっている”よりも、書くことに対してこんなにも考えなきゃいけないのかと畏れが増すような。書くマインド・セットについての記述が多い気がしますが、個性とはクセの集積という点は大事にしようと思いました。うちのブログは一応、文体とかセレクトとかで他にない個の要素が強い音楽ブログにしようというのはあるんですけどね。それに誰も書いてないところを書いていますし。
どんぐりの背比べ的な状態から頭ひとつ抜け出すには、もちろん最初から非凡な才能に恵まれているなら別ですが、残念ながらそうではなくて、それでも自分が作り出したものを他の人たちが作ったものから差異化したいのならば、 個性を、すなわち何らかの意味での個別性・特殊性を、ユニークネスを獲得する必要があります
『書くことの哲学』より引用
レジー『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
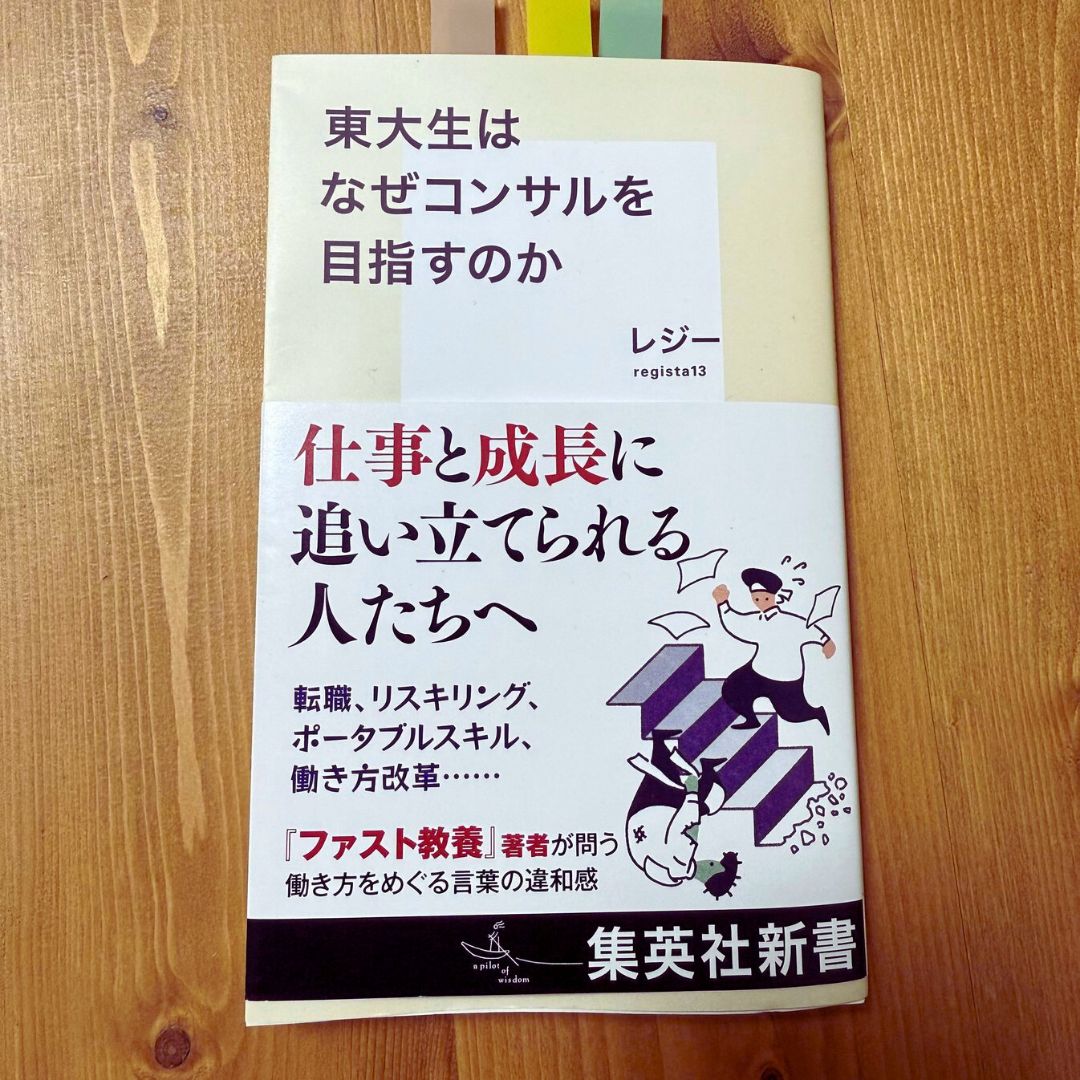
本書では”成長教”と表現されているほどで、読んだら成長という言葉を禁じられた気になりますが、前著の『ファスト教養』と同じく現代社会の風潮を理解できるような一冊かと。安定するために成長する。目的はわかるが、そこにどういった主体があるのかはよくわからない。漠然と社会に駆り立てられてそうなっている気がする。
”我々は必要以上に成長を促されるベルトコンベアに載せられている。それに対して自分のキャパシティーを超えて無理に適応しても、待っているのは心身の疲弊である(p210)”。地に足つけて生きる。自分にとっての大切なことを見つける。その難しさはSNS時代に余計に上がっている。
ゴールイメージからやるべきことを定義して、そこに高速のトライアンドエラーをかぶせることで「売れる」もしくは「バズる」アウトプットを磨いていくのが今の時代に最適化したミュージシャンのあり方である。この背景にあるのは、音楽業界の「IT産業化」だろう
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』p165より
IT産業化というのはあらゆる指標が数字になることでもある。フォロワー数、インプレッション、リポスト数、再生回数・行動の結果が数値として提示され、それを追いかけて改善するのが当たり前になる。これは言い換えると日々の成長が見えやすいということでもあり、この構造に最適化した人々は数字を伸ばす中毒に陥っていく。「売れる曲といい曲”はイコールなのか?」といった問いは昔から存在するが、そんな疑問を挟む余地がないくらい現在の音楽業界では数字の力が強くなっている。この状況を飲み込めるかどうかが、今の時代に良いミュージシャンとして名を馳せられるかの分岐点となる(p166)
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』p166より
周司あきら『男性学入門』
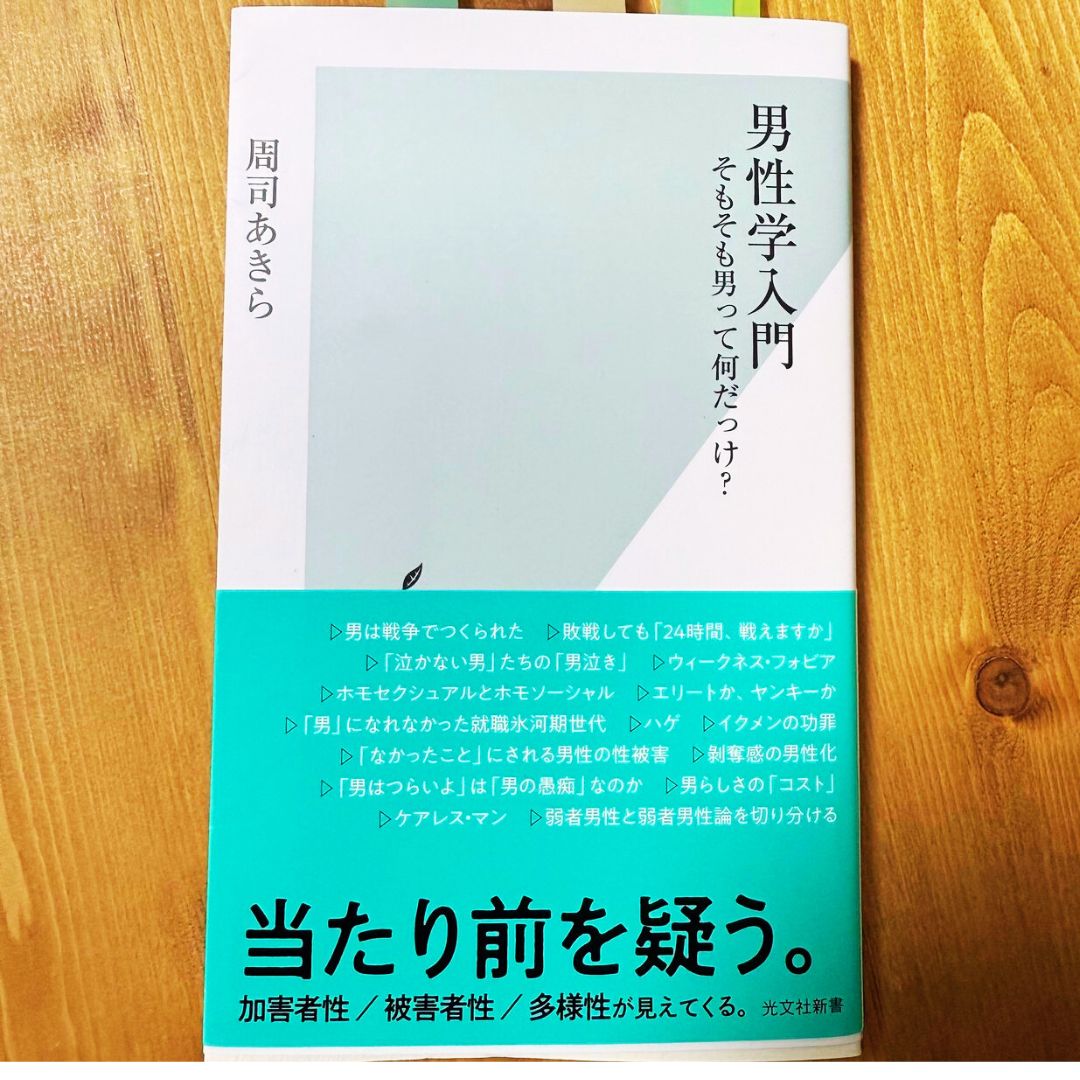
男性学とは、男性の当たり前を問う学問です(P4)
この系統の本はそこそこ読んでますが、本書は上記にある通り基本的なところを学べます。男らしさ、男性史、メンズリブ、家父長制などなど全6章に渡り、改めて男性について考える。
①男性の制度的特権(男性の加害者性)
②男らしさのコスト(男性の被害者性)
③男性内の差異と不平等性(男性の多様性)
p116においてこれら3つの視点を持つことが重要だと述べていますが、意識していくことだなと思ってます。ジェンダー的な表現は当ブログでも気を付けていますがね(いろんなことを本なり映画なりニュースなりで知っていかないと、このブログは書けないです)
特定の男らしさがもてはやされるときには、実はその裏で、これまで通り男性にとって都合のいい仕組みが維持されているのではないかと、注意深く観察しなければいけません。
『男性学入門」』P48より











