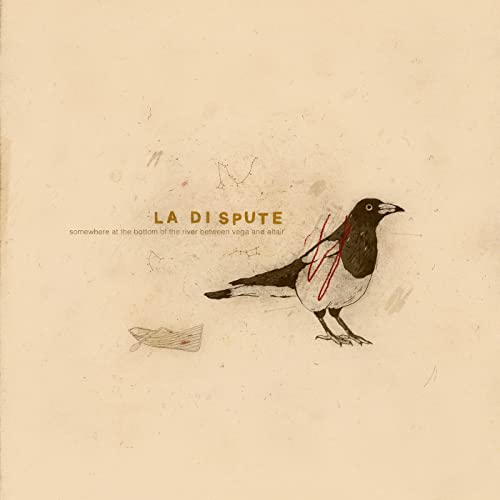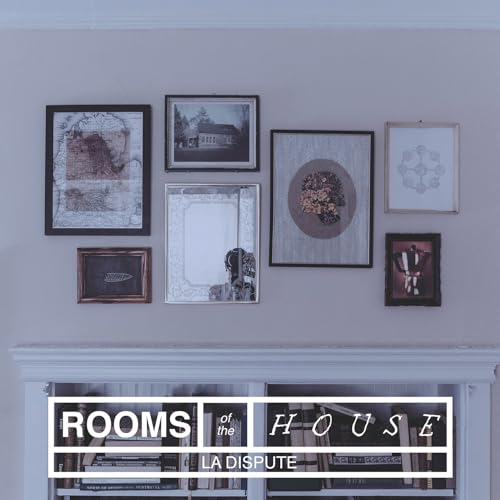2004年にアメリカ・ミシガン州グランドラピッズで結成されたポストハードコア5人組。中心人物であるJordan Dreyerが高校在学中に結成。バンド名は、Jordanが高校時代に観たピエール・ド・マリヴォーの戯曲『La Dispute(いさかい)』に由来する(詳細が知りたい方にはHard Forceのインタビューが参考になる)。ちなみにJordanとドラマーのBrad Vander Lugtが従妹関係にあたる。
RefusedやFUGAZI、At The Drive-Inといったバンドに影響されたサウンド、ウラジミール・ナボコフやアラン・ポーといった著名作家に影響された詞、それを語りと叫びを組み合わせたポストハードコアで表現する。
初期はマスコアにも近いスタイルでしたが、徐々にストレートな作風へと向かい、4thアルバム『Panorama』では電子音やホーンセクションを導入。これまでにフルアルバムを5作品発表していますが、アルバム毎に少しずつ変化を遂げている。またスポークンワードのみで構成された実験的なEP『Hear, Hear. 』を定期的にリリースしている。
本記事は2025年9月にリリースされた最新作となる5thアルバム『No One Was Driving The Car』を含む、フルアルバム全5作品について書いています。
作品紹介
Somewhere at the Bottom of the River Between Vega and Altair(2008)

1stアルバム。全13曲約51分収録。2024年に閉鎖されたNo Sleep Recordsからのリリース。UNDER THE GUN REVIEWによるリリース当時のインタビューを参照すると、本作は中国の神話『牛郎織女』をストーリーに取り入れている。日本でいうと七夕の織姫と彦星の話だと捉えてもらえればよいかと思います。天の川のような障害物、男女の失恋・別離をモチーフにしており、3曲は2組の離婚を扱った曲だと説明する(#3、#7、#11の3曲。参照:mvremixインタビュー)。
クリーントーンのギターとスポークンワードで90秒で沸点へ導かれる#1「Such Small Hands」を皮切りに、強烈な衝動をもたらす曲が本作には揃います。しかし、初のフルアルバムにしてLa Disputeの中では一番異質かもしれません。ポストハードコアを基盤に置いていますが、ストレートな軌道を走りつつも変則的な展開を多分に入れ込み、直線と曲線を上手く使い分ける。
その様はマスコアまでいくものではないにしても、場面によってはジャズやメタル、ポストロックといったものとハードコアがセッションしているかのよう。そして、中心に置かれるヴォーカル兼作詞家のJordan Dreyer。彼のスタイルは”語りと叫び”と端的に表現できますが、それらを用いて情熱と緊迫感を生み出している。またコーラスワークの活用も次作以降と比べるとかなり多い。
サウンド面ではAt the Drive-In、Glassjaw、Refused。歌詞ではJoanna Newsomに影響されたと後のインタビューで語っています。本作は前述した中だとRefusedは近い印象があり、#3「New Storms for Older Lovers」は影響を特に感じさせる曲。それにThese Arms Are Snakes的な感触もあったりしますし。
また七夕に関連してか、ジャケットに刻まれた”7″は先のインタビュー内でアルバムの音楽的構成にも登場すると話しています。#4「Damaged Goods」や#12「The Last Lost Continent」で7拍子のパートが登場するのはその関連といえそう(歌詞では”Darling”という単語が良く出てきますが、こちらは集計したら7回ではなく8回でした)。
タンバリンと小気味よいリズムに乗せて爆発的な瞬間を生み出す#2「Said The King To The River」、中間部のキメのフレーズに痺れる#7「Last Blues For Bloody Knuckles」、やや暗めの曲調の中で別れた彼女のことを執拗に思い続ける失恋ソング的な#9「Andria」は印象的な楽曲。そして約12分に及ぶ#12「The Last Lost Continent」は、湿っぽいギターの音色を中心に織り上げ、Jordanの語りと叫びが胸を突いてくる。
2018年には10周年を記念したリイシュー盤がリリース。またイギリスの音楽誌であるRock Soundが2012年に発表した【101 Modern Classics 1997-2012】の53位にランクインしている。
Wildlife(2011)

2ndアルバム。全14曲約58分収録。引き続きNo Sleep Recordsからのリリース。THE DAILY TEXANの記事によると”Wildlifeというタイトルをつけたのは、あらゆるものを包括的に表現できる言葉だからだと思う。私たちはみな、悲劇と変化を目の当たりにする。それは私たちの存在の総和である。“とタイトルについてJordanは述べています。
本作はaの単語から始まる4つのセクションに別れており(#1「a Departure」、#5「a Letter」、#8「a Poem」、#12「a Broken Jar」)、その構成はウラジミール・ナボコフの『青白い炎』にインスパイアされているそう(参照:redefineインタビュー)。ちなみにJordanは他にもカート・ヴォネガット、エドガー・アラン・ポー、トム・ロビンスといった作家からの影響を公言している。
前作と比較するとストレートな曲調が増えています。また、ライブで聴いた時の自然な音を捉えられるものにしようと人工的なリバーヴを一切使わないという制約を設けて制作。高速ドリフトを繰り返すようなスリリングさは減退したものの、歯切れの良いリズムや生々しく性急なギターが感情をブーストさせます。そして血管と喉仏へのダメージもいとわない絶叫、聴衆の興味を引くようなスポークンワードが聴衆を何よりも駆り立てる。
構成を少し簡素化したことで、曲の持つストーリーを伝えることに重きが置かれています。人生における苦悩や悲劇や喪失、それらの対処についてフィクションと実体験を交えながら書かれているそう。そして故郷・グランドラピッズの実在の出来事も混じっている。
#3「St. Paul Missionary Baptist Church Blues」は実在するグランドラピッズにある廃教会、#10「Edward Benz, 27 Times」は統合失調症の息子にナイフで襲われた父親、#11「I See Everything」は7歳の息子を病気で亡くした両親と信仰について描いています。
そしてSpotify再生回数が3000万回を超える代表曲#10「King Park」は、JordanとドラマーのBradが当時に働いていた場所のすぐ近くで起きた銃乱射事件によって、罪のない子供が亡くなったことが題材。こうした痛みと悲劇は遠い出来事ではなく、身近でも起こりうると骨身を削って表現している。
本作はビルボード200にて135位にランクインしており、La Disputeの中でおそらく最も人気の高い作品です。
Rooms of the House(2014)
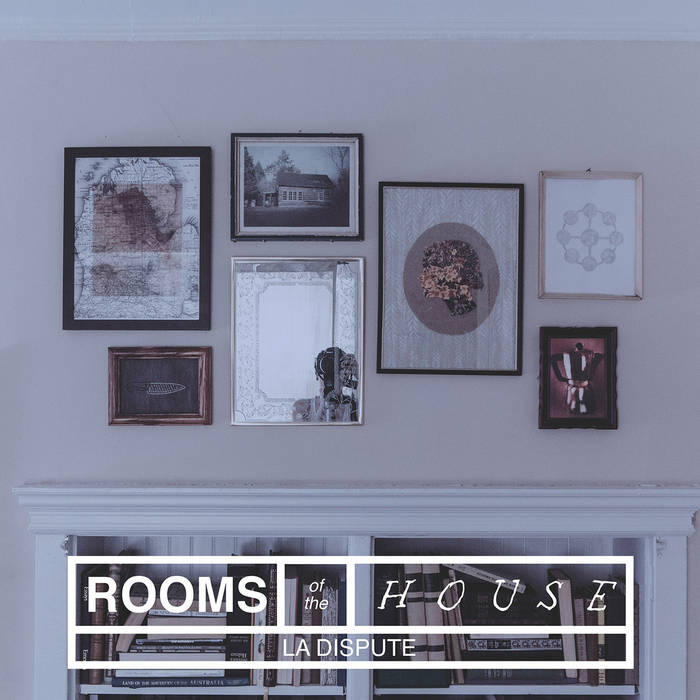
3rdアルバム。全11曲約42分収録。自身のレーベル、Better Livingからのリリース。またプロデューサーにWill Yipを招いての制作。ミシガン州北部の人里離れた山小屋で曲作りをした後、レコーディングを敢行しています。
NEW NOISE MAGAZINEやVICEのインタビューを参照すると表向きは架空のカップルの話ですが、ある家の部屋や物が持つ歴史や共有された記憶がコンセプト。それをタイトルにも反映している。例えばコーヒーメーカー、ラジオ、本。それらを見たり、触れたりすることで何かを思い出す。このように物や部屋が、そこで起こった出来事や経験を包み込むようになることを描いている(フィクション中心ですが、Jordan Dreyerの家族の歴史が混ざったものではあるらしい)。
前作以上に要素をさらに削いでシンプルな音楽に向かっており、ミドルテンポの曲が多め。5拍子ながらもノリ良く進む#2「First Reactions After Falling Through The Ice」、1stアルバムの雰囲気を思い出す#7「Stay Happy There」といった曲があるとはいえ、ハードコア寄りの激しさは抑えられています。スポークンワードを中心に緊張感を保っていますが、声を荒げる回数は減っている。
代わりに軽快なコード進行やメロディアスな音色が柔らかなトーンと哀感を連れてきます。そんな中で”私が書いた中で最もストレートなラブソング“と自身で謳う#3「Woman(in mirror)」、しんみりした曲調が沁みる#6「35」といった曲が新鮮に響きます。また中盤を飾る#8「THE CHILD WE LOST 1963」は、ポストハードコアとスロウコアを行き交う曲調の中で、Jordanの祖母が流産した時のことを歌詞にしている。
本作は一歩引いたレンズで部屋を映し出す中で、バンドの繊細な領域を新たに掘り起こしています。#9「Woman(reading)」には”君がこの家を出ていくときに所有物を全て持っていくけれども、思い出はこだまする“と記される。カップルの関係が破綻したあとでも部屋や物から記憶が呼び起こされる、そんなアルバムのテーマを最も表しているように感じます。個人的には大崎善生氏の小説『パイロットフィッシュ』の冒頭文を思い出したり。
Jordanは”これは前に進むことについてのアルバム“だと語っていますが、人はそれぞれ固有の記憶や経験を基に生きていく。それを改めて思い直させる作品であると感じます。
Panorama(2019)

4thアルバム。全10曲約42分収録。Epitaph Recordsへ移籍。プロデュースにWill Yipが引き続き携わっています。本作はグランドラピッズから郊外のローウェル(Jordanのパートナーの故郷)へ向かうドライブが基になっている。
”あのドライブのことをずっと考えていた。それが最初のきっかけで道沿いの追悼碑を見たり、パートナーの話や彼女の家族と知人の話を聞いたりした。アルバムの全てはこの長いドライブの中で起こっている。『Wildlife』とは喪失や悲しみ、それに対処するメカニズムといったテーマが共通している“とsaved by old timesのインタビューで回答。
歌唱にしても音にしても本作からは抑制と洗練という表現が浮かんできます。#1「Rose Quartz」に代表される控えめな電子音の装飾、#4「Rhodonite and Grief」におけるホーンセクションの導入。そしてJordanの語り口はゆっくりと諭すことが増えている。これまでに使ってない楽器やレイヤーを試したかったという本人の説明はありますが、激しめのパートは限定的でアルバム全体が繊細な色合いを帯びています。詞ではなく音の方で行間を表現しているような印象でしょうか。
象徴的といえるのは#2「Fulton Street Ⅰ」~#3「Fulton Street Ⅱ」の流れ。つぶやくように言葉をつらね、侘しいギターの音色が寄り添う中でポストハードコアが随所に凱旋する。こうした強弱のアップダウンを繰り返しながら、曲名にある場所で起こった出来事とその悲しみについて描写しています。
自己と他者の内面に潜りこむ。喪失感を星座のように点と点で結ぶ。その快復を言葉と音で編む。そんな本作についてJordan DreyerによるKerrang!の全曲解説が理解の手助けになります。誰もが今この瞬間に感じる不安を捉えようとしたと語る#5「Anxiety Panorama」、自身のパートナーの好きなフレーズを曲名にした#9「There You Are」、そしてラストを飾る唯一の長編#10「You Ascendant」。いずれも穏やかさの中から力強い叫びが響き渡った瞬間、昂ぶりを覚えます。
人生を通して死を静かに抱え込み、避けられない終わりと調和を図ること。『Panorama』という悲しみの巡礼は、生死の儚さをより深く見つめ直すきっかけとなる。
No One Was Driving The Car(2025)
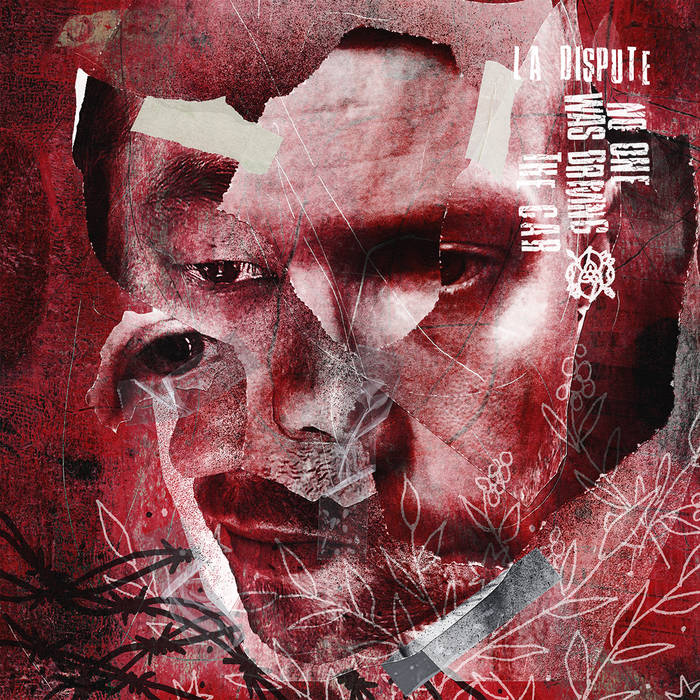
5thアルバム。全14曲約64分収録。Epitaph Recordsから引き続きリリース。約6年ぶりとなる本作はセルフプロデュース作品です。タイトルは2021年4月にアメリカ・テキサス州で起こったテスラ自動運転車による2名の死亡事故。この件に関する警察官の発言から引用(参照:GIGAZINE記事)。
本作は映画から強いインスピレーションを受けており、ポール・シュレイダー監督の『First Reformed(邦題:魂のゆくえ)』を特に強い影響元として挙げています。映画を念頭に置いたアプローチからアルバムは全5幕で構成され、それを1幕ごとに年間通じてリリースしていく形態をとりました。UPROXXやKerrang!、Hard Force等のインタビューを参照すると、孤独や環境危機、信仰と宗教、マルチレベルマーケティング、資本主義社会といったテーマを織り込んでいる。
”これまでの集大成だと思う。すべてのアルバムの要素が少しずつ詰まっている(前述のKerrang!インタビューより)”とJordanは端的に作品を評します。確かにアルバム毎に変化しているバンドだけに、その発言は本作のコレクティヴな作風から納得がいく。しかし、映画のセリフのサンプリングをここまで大々的に引用するのは初めて。それにアルバムの中核を成す#4「Environmental Catastrophe Film」にはRadioheadが背後霊のようにうろつき、#6「The Field」の終盤でドゥームメタルに挨拶する。総決算という趣ながらも新鮮な要素をいつも通りに取り入れています。
また前作と比べるとエレクトロニックな装飾はほぼ無くなり、バンド感の強い音楽に戻っている。それはパンデミックから抜け出すための『Wildlife』と『Rooms of the House』のリリース10周年記念ツアーの影響が大きかったとのこと。特定の過去が蘇らせる感情と音。それが現在と未来に結びつく。サウンドはハードコアとアコースティックの狭間で揺れ、リリース時点で38歳を迎えたJordan Dreyerによる語りと叫びと詩は一級品に磨き上げられている。表現の芯は全くブレていません。
頭を剃る行為を通して自己のリセットを試みる#1「I Shaved My Head」、ねずみ講に巻き込まれた若い女性の物語を綴った#8「Landlord Calls the Sheriff In」、一緒に過ごした時間を振り返る形で自殺した友人について書いた#9「Steve」といった緊迫感のある楽曲が揃う(ちなみにグランドラピッズの近くに本社を構えるのがア○ウェイ)。そういった中でアルバム全体で捉えようとしているのは混沌とした現代社会の不安、テクノロジーの進化と功罪です。
”人生の不安定さと、権力の舵を取る者たち、つまり私たちのコントロールを超えた外部勢力による、『人よりも利益を優先する姿勢』への懸念が高まる中で、私たちがどのように影響を受けているかを認めるかが重要だった“とJordanはKerrang!で語っている。
最終の第5幕にあたる2曲はアコースティック主体で、上記の内容を含んでいます。#13「No One Was Driving The Car」の胸が張り裂けるような絶唱、対照的に#14「End Times Sermon」でのさみしげなつぶやき。後者では終盤に”私たちは世界で最も裕福な国にいる。それでも私たちは最も貧しい。自分の孫たちを見て、そして他人の子供たちを見て、彼らには一体どんな明日が待っているのだろう“という痛切なナレーションが入り、憂いに包まれたまま幕を閉じている。
こうして個人レベルのものから、より強い社会的な視座を持った作品へと昇華。La Disputeは円熟した表現と緻密に練り上げられた構成によってそれを実現しています。