
1995年に結成されたチェコのポストハードコア/ポストメタル・バンド。創設メンバーであるHusar(Vo,Key,Sample)を中心に結成され、30年の歴史を誇ります。
Neurosisの影響下にある重厚で壮大な作風、1967年のチェコ大作映画『マルケータ・ラザロヴァー(Marketa Lazarová)』の引用を中心とした映画からのサンプリングを組みわせた独自のスタイルで、カルト的な人気を今も集めています。
バンド名はもともとLumen(光の単位)と名乗っていたが、ラテン語綴りの”LVMEN”が後に採用される。LVMENが意味するものについてはKIDS&HEROESのインタビューで、”光、光束の単位。私たちの本来の自然さ。つまり、まさに兵士シュヴェイクが体現していたもの“と答えている。ちなみに読みは地元チェコのニュース誌、RespketのYouTubeにて”ルーメン”と読んでいるのが確認できる(参照:こちらの動画 23分12秒辺り)。
本記事はこれまでに発表されているフルアルバム5作品、EP1作品について書いています。なお曲名についてはローマ数字が環境依存文字になるため、本記事では通常の数字で表記しています(下記にて補足)。
※ LVMENに楽曲タイトルは存在せず、「Ⅰ」「Ⅱ」などローマ数字による通し番号で表記している。この理由についてMETALOPOLISのインタビューによると”曲名ではなく番号を付けるのは、以前は歌詞が全くなかったからです。ボーカルは音楽の補足的な要素で、まるで別の楽器のような存在でした。曲の番号付けは最初のEPで「1」と「2」という曲名から始まって、その後も継続。私たちのグループの全体的な匿名性を反映した伝統となりました“と回答しています。
作品紹介
Lvmen(1998)
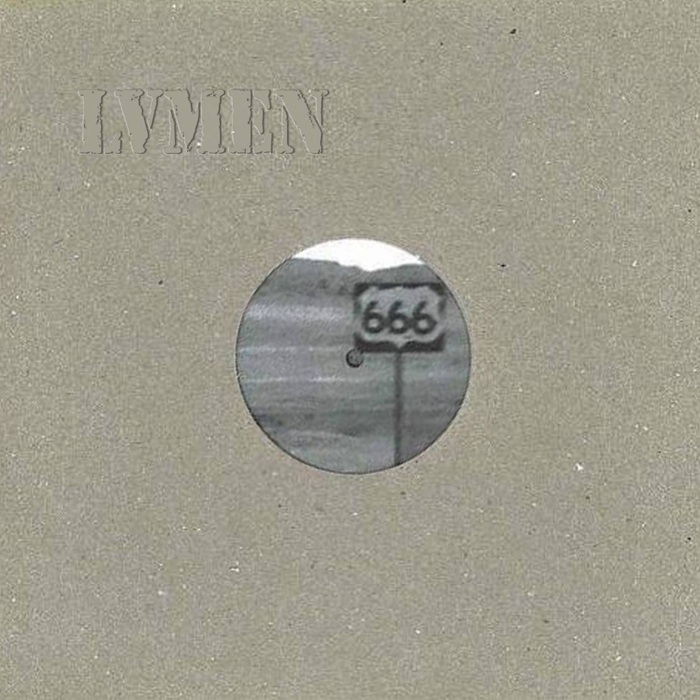
1st EP。全2曲約28分収録。チェコと言えばカフカ、ロシツキー、そしてこのLVMEN。知られざる怪物バンドであり、カルト的な人気を一部で誇ります。
本作の収録曲は#1「1」が約13分半、#2「2」が約14分半といずれも長尺。活動初期のEPとはいえ、これら2曲でLVMENの基本的な音楽性は説明されています。ポストハードコアをベースにして、NeurosisやGodspeed You! Black Emperor、Hooverといったバンドと接続しながら、長い時間をかけて大きくうねる。
穏やかな旋律と荒れ狂う大河のような轟き。呪術的な祭事の側面を強めるリズム。複数名が担当するスポークンワードと苦悶の叫び。そして、本作から以降の作品でも続いていく映画から引用するセリフ・サンプル。それらの混交が超然たる力を持って迫ってくる。
#1「1」の3分過ぎに入るトランペットや奇妙なエフェクト。#2「2」では冒頭における宇宙衛星と交信するような効果音から映画『ナチュラル・ボーン・キラーズ』の「Route 666」の引用を挟み、所々で狼の遠吠えが挿入される。その上で2曲ともに絶望と対峙する音の壁が築かれており、人生にトラウマレベルでこびりつくほどの脅威となる可能性を秘めています。
当時はポストロックやポストメタルという言葉は一応ありましたが(世間的に浸透はしていない)、ISISやCult of Lunaが活動初期段階で、MOGWAIもGY!BEも1stアルバムを出したばかり。そんな中でLVMENは知られざる存在ながらも後続に踏襲されていく作品を既に生み出していたわけです。
Raison D’Etre(2000)

1stアルバム。「3」~「7」までの全5曲約41分収録。LVMENの永遠のインスピレーション基となる1967年のチェコ大作映画『マルケータ・ラザロヴァー(Marketa Lazarová)』との結びつきを強め、ブックレットでは同映画の冒頭シーン(狼が群れとなって雪道を走る場面)を使用。また#1「3」の3分20秒辺りで映画第一部の終盤近くにある老女が”狼に育てられた人間が、人間のせいで狼になった~”から始まるセリフを長めに引用しています。
約1分の短い間奏曲である#3「5」を除くと8分半~11分までの楽曲で構成されており、じっくりと雰囲気を作り上げていくのは前作から変わりません。ただし、#1「3」を始めとして叙情的な旋律が引率役を果たすシーンが結構あって、意外には感じます。それに読経やオペラ歌唱、神経を惑わす効果音が本作では取り入れられており、映画からのサンプリングも引き続き随所に散りばめられている。
そういった表現によって聴覚から瞬間的な映像効果を受け取ります。一方でどんよりとした陰鬱な雰囲気、バンドの根源にあるハードコアの野性味気質がぶつかりあう。実験性を加味した上での構築された美しさ、生々しい衝動が封じ込められた#1「3」はLVMENの代表曲のひとつ。そして、大量の蟲による不快な羽音らしき始発点から10分半をかけ、荘厳なクワイアによって導かれる終着点に辿り着く#5「7」。こちらもまた五感をぶっ叩く楽曲です。
Neurosisの子孫系バンドとはいえるのですが、チェコ文化との結びつきやハードコア的な側面をより発揮することで独自のスタイルを開眼。『Raison D’Etre』は、この界隈で貴重な影響力を持つ重要作です。なお、前出のEP『LVMEN』と本作を併せて全7曲約69分収録&リマスターを施した編集盤を2006年に発売しています。
Mondo(2006)

2ndアルバム。#8~#13までの全6曲約39分収録。3年間の活動休止を経て、6年ぶりとなるフルアルバムです。Metalopolisのインタビューによると、本作には『マルケータ・ラザロヴァー』の他に『ビフォア・ザ・レイン』、『チベット死者の書』から引用されているという。
基本的にこれまでの音楽性を踏襲したものですが、10分を超える曲はなく、楽曲は少々コンパクトになっています(ただし、平均で6分30秒あります)。かといって感動や芸術に単純ワープするようなものではなく、細かくグラデーションを成す丹念な構築によって深い陶酔と昂ぶりをもたらす音楽です。
ポストロック的なニュアンスの強いツインギターで織り上げていく#1「8」に始まり、複数体制による狂気じみた叫びが連続する#2「9」は精神を罵倒してくるかのようで強烈です。加えて『マルケータ・ラザロヴァー』からの引用も#3「10」の2分10秒辺りに盛り込まれている(修道院でマルケータが”神よ 死者はあなたを賛美できません“と神の存在を見限る2時間39分辺りのシーン)
聖と邪。落ち着きと喧騒。冷静と情熱。対となるものを巻き込みながら創造される音、そして非現実な世界。中盤に突如としてConvergeにも似た形相で迫りくる#6「12」、しめやかなレクイエムと思いきや破壊と悲劇が一蓮托生となる#7「13」も心の芯を薙ぎ倒してくる。前作に引き続き壮絶な体験を約束する作品。
Heron(2008)

3rdアルバム。#14~#21までの全8曲約50分収録。彼らの中では、かなり短い約2年のスパンで届けられたことにまず驚き。そして、フルアルバムとしては最も長い収録時間となります。ジャケットに描かれているのは、Heron=鳥類のサギだと思われる(バンドからの具体的な説明はないので、憶測です)
特徴的なのは他の作品と比べてインストゥルメンタルが主体であること。また自身の肉声で表現しているシーンは少なく、代わりに映画からのサンプリングが多めです。冒頭を飾る2曲は完全にインスト。#1「14」と#2「15」は1つの楽曲のように感じられ、神妙なアンビエント・トラックとして機能している前者から、ハードコア・テイスト全開の後者へとつながる。
アルバム最長となる#3「16」は11分に及びますが、十八番の映画からのサンプリングと繰り返されるクリーンなギターサウンドで緊張感を高めながら、炸裂と解放の瞬間が生み出される。彼らにしては珍しいロックンロールな勢いとサスペンス色を組み合わせた序盤から、その後も変則的に場面を切り替えていく#7「20」もまた一驚。
こうして攻撃的なインパクトは随所に残しているものの、生きる座標軸を見失ったかのような虚無がまとわりつく。うつろなベースラインからスタートする#5「18」、00年代のNeurosisに渋い風合いを加えた#6「19」といった中盤の曲は変化を感じさせる部分です。
LVMENのカタログの中でも聴かせる作品に属し、明りに頼れないほどの暗闇の中で、鎮静と思慮を促すパートは多い。だからといってじっくりと聴き入るものでもなく、精神と相談しながら『Heron』の世界と向き合う必要があります。
Mitgefangen Mitgehangen(2017)

4thアルバム。基本的には#22~#25までの4曲約34分収録。タイトルはドイツ語の慣用句で”一緒に捕らえられれば、一緒に絞首刑にされる“という意味。ALTERECHOのインタビューによるとチェコスロバキアの連続ドラマ「Lekár umierajúceho času(DeepLの日本語訳だと”死にゆく時代の医師”といった意味合い)」のセリフからアルバムタイトルを拝借したと発言しています。
9年という時間は世界をガラケーからスマホへ変えてしまうぐらいの長さ。そんな中で前作から本作までに9年もの期間を要した大きな理由はギタリストが亡くなり、ラインナップの変更があったためです。付け加えますとLVMENは中心人物のHusarを除けば、誰がメンバーなのかよくわからないぐらいに入れ替わりが激しい。
それでも、畏怖と脅威が同時に襲い掛かるLVMENの音像は不変です。啓示のごときスピーチサンプルから、ギターとベースのユニゾンで地鳴りのごときサウンドを展開する#1「22」。この幕開けからして代替不可な巨大な存在に賛辞を送りたくなる。
本作は前出のインタビューを参照すると『Heron』の続編的な意味合いを強く持っているとのこと。確かにムード重視という部分は前作に続くものです。しかしながら、リフやリズムにおいてハードコアに根差したバンドの肉体性の復権は感じるところ。クレジットではゲスト参加が多いようなのですが、声にしろ演奏にしろ感情的な蠢きが前作よりも反映されているのは惹かれます。
Cult of Lunaの渋い歌もの曲に通ずる#3「24」は、ドラムを中心として終盤に畳みかける展開を牽引。また『マルケータ・ラザロヴァー』の1時間55分辺りの宣戦布告シーン”王は我々の君主だが、戦こそが王の君主だ“から始まる#4「25」では、男女デュエットの安らかさを覚える歌ものからNeurosisに追随する暗黒までの多様性を表現。国内外からカルト的な尊敬を集めるバンドとしての復帰作として、十分に使命を果たしています。
ちなみに冒頭で”基本的には”と記したのは1st EP収録の最古の楽曲「1」が、なぜか再録されているからです。大まかな構成は踏襲されている中で1分短くなり、原曲のライトな聴きやすさを排除。代わりに重厚・暗鬱・呪詛の三要素が増し増し。新編成で再録した意義はもちろんあるのですが、わたしはLVMENを初めて聴いて衝撃を受けまくったのが「1」なので、原曲派です。
Amen(2025)

5thアルバム。#26~#29までの全4曲約37分収録。長き眠りについていた怪物が結成30年目に再び目覚める。その帰還を我々は崇め奉ります。
チェコのニュース誌であるRespketのインタビューで本作について”私は『Amen』という言葉を最終的なものとは考えていません。ミサの最後に参加者が集団の恍惚状態になり、それを持ち帰る時に発せられる言葉なのです“と語っています(ただ、インタビュー記事は月額サブスク課金しないと全文読めません)。
ずっと陽の当らない場所で冬眠していたとしても、時がLVMENを止めることはできない。#1「26」において散りばめられる効果音と映画を中心としたサンプリング、屈強なリズムワーク、苦悶の叫び。『マルケータ・ラザロヴァー』との時空を超えたつながりも#2「27」で継続(“剣を持つ敵に襲われたら 当然 剣で応える“という1時間49分辺りのシーンを引用)。自身の核となる表現を盛り込みながら、楽曲によってはAmenraのような儀式的要素が本作では増しています。
特にその影響が出ている#3「28」ではタイトルにある”アーメン”を含む聖歌隊を冒頭でサンプリング。そのままタメの効いたのっぺりとしたムードが続きますが、中盤5分辺りからの女性によるセリフを挟み、混沌とした激しさを一気に増してクライマックスまで暴れまわる。終盤の警告を訴えるギターソロや一瞬だけ人間を辞めてしまったかのような雄叫びには感情がピークに達すること必至。
これまで以上にスラッジメタルの重量感があるのも特徴で、リズムも過去作と比べて最も強靭。その上でLVMENはハードコアの熱や動性を手放さず、良い塩梅で組み合わせる。10分を超える#4「29」ではLVMENのダイナミックな揺れ動きが余すところなく表現した上で、祈りと解放のクライマックスへ。
厳粛でいて力強い。30年を迎えてもなお、LVMENが重厚さと威厳を保ち続けていることを本作で証明しています。はたして通算30曲目は何年後に生まれるのか。それとも生まれずに終わってしまうのか。また長い年月、彼らの帰還を待ちたいと思います。





