
1999年に東京で結成された4人組ポストロック/インストゥルメンタル・バンド。Takaakira “Taka” Goto氏を中心にYoda氏(Gt)やTamaki氏(Ba)をオリジナルメンバーに、2018年からはアメリカ人ドラマーのDahm氏がラインナップに連なります。
彼等は世界で最も聴かれている日本のバンドのひとつ。これまでに毎年100本以上にも及ぶ海外公演を行い(逆に日本公演が年に2~5本ぐらいしかない)、総計59ケ国に及ぶ地で演奏しています。さらにThe CureのRobert Smithのキュレーションによって2018年6月に開催された『Meltdown Festival』にて日本人として唯一出演するなどの実績もあり。
もちろん、それだけにとどまらずに世界中の音楽フェスに出演しています。日本のポストロック、インストゥルメンタル・バンドの第一人者として、最前線での活躍をずっと継続しているのです。
これまでに12枚のアルバムをリリース。さらに10周年と20周年にオーケストラと共演したライヴアルバムを2作品残しています。その音楽性は轟音インストゥルメンタル・ロックにクラシックや映画音楽、さらには日本人の情緒が重ね合わさったもの。
「神の音楽」とUK雑誌NMEにて評され、4thアルバム『You Are There』のレーベルインフォには 「MONOはブラックサバスのようにへヴィーなのではない、ベートーベンのように重厚なのだ。」という言葉が添えられるほどです。
わたし自身、地方在住ながらもMONOのライヴを体感しに10数回は遠出していまして、毎度圧倒されています。単独公演だって、10周年のオーケストラ公演だって、2012年のフジロックだってそうでした。
本記事は彼等のオリジナルアルバム12作品、そしてオーケストラとのライヴアルバム2枚について書いていますMONOのライヴを一度は体験してほしいと思うのですが、まずは本記事を通して彼等を聴くきっかけになれば幸いです。
アルバム紹介
Under The Pipal Tree (2001)

1stアルバム。全8曲約63分収録。日本からではなく海外からそのキャリアをスタートさせたMONO。John ZornによるTzadik Recordsからワールドワイド・リリースされています。
ツインギター、ベース、ドラムというシンプルな4人編成。MOGWAIやExplosions In The Skyに系譜する静寂と轟音の両輪を主体に、美しくも荒涼とした壮大なサウンドスケープを描きます。
繊細なギターの音色が底冷えするような冷たさと哀感を抉り出し、ピンと張り詰めた緊張感の中でタメにタメた轟音によって、風景を荒々しく塗り替える。喜びや悲しみや怒りや憂いなどを纏いながら、言葉を超えて、力強く聴き手の胸のうちへと届きます。
全8曲収録されていますが、10分超の曲を3曲も収録。静かで精微なアンサンブルからバンド自身の幕開けを告げるかのような轟音へと発展していく#1「Karelia」、凍てついた静寂の中で膨れ上がった哀切や悲しみが、フィードバックギターの轟音に乗せられて徐々に昇華され、光へと変わっていく#2「The Kidnapper Bell」の頭2曲が特筆すべきもの。
また#2を頂点にして、徐々に労りや安らぎといった色調が強くなり、人々の悲しみを慰謝する方面に向かっているように自分は感じます。
本作で特に感じられるのは、荒々しい初期衝動。音色のひとつひとつに込められた感情(特に”怒り”が強いように思う)の揺れは、不安定な脆さも見せていますが、決意のこもった力強さを最後には示しています。
MONOのプロトタイプともいうべきものが表現されており、ここから特有のスタイルは形成されていくことになります。
One Step More and You Die (2002)

2ndアルバム。全8曲約51分収録。不条理、孤独、怒り。そんな負の感情が創作の源になっているのを明らかに感じます。1stアルバムがベースになっていますが、猛烈な怒りと反骨心は、絶望的な色の濃い楽曲に表れている。それでもなお、希望を何とかして描こうとする姿勢があります。
その具現化が16分近い大曲である#2「Com(?)」です。Mogwaiの「My Father My King」を彷彿とさせる凄まじい轟音体験がありますが、もっと生々しくてもっと残酷でもっと絶望的。
音に満ちた殺気、全ての矛盾と不条理を葬り去ろうとせんノイズの結晶体は、ふきすさぶ嵐となって聴き手に襲い掛かります。でも、実はとてもドラマティックでもあります。残響音のあとに焼野原となった荒野で傍観するような終焉には虚無感を覚えるのみ。
安息をもたらすように掻き鳴らすトレモロが印象的な#3「Sabbath」、世界の終わりがよぎる#4「mopish morning, halation wiper」、本作中ではもっとも明度が高く柔らかな日差しが降り注ぐ#6「loco Tracks」。序盤で噴出した負の濁流は和らぐものの、どこか諦念を抱きながら希望を何とか見つけ出そうとしている感覚があります。
#7「Halo」が鳴らす美しいノイズは打ちひしがれるような哀しみの果ての祈りでしょうか。現状への反抗と闘争、もがき続ける中で存在証明としてノイズに全てを託す。その人間臭さ。戦うバンドであり、冒険するバンドであることを徹底的に音に込める。
これ以降の作品ではクラシックの要素が融合されていきますが、本作における生々しい感情の猛りは初期の彼等だからこその表現となっています。
なお、本作は「世界の終わりのサウンドトラック」と世界中で賞賛され、2003年にアメリカ音楽雑誌のAlternative Pressにて、”TOP 10 ESSENTIAL INSTRUMENTAL METAL ALBUMS “にも選ばれました。MONOが着実に世界でその効力を広げていることが伺えます。
それにしても10数年、演奏していなかった「Com(?)」が2019年の20周年ツアーにてラストを飾る曲になる。歴史は巡り、バンドも変化していく。わたし自身、MONOのライヴは単独公演もオーケストラ公演もフジロックも含めて何度も見てますけど、After Hours ’19で「Com(?)」を初めて体感した時はかなり衝撃的でしたね。
Walking cloud and deep red sky, Flag fluttered and the sun shined (2004)

3rdアルバム。全8曲約58分収録。長く歩みを共にするTemporary Residenceとの契約、そして盟友でもあるスティーヴ・アルビニとの共作は本作からスタートしました。
またクラシックや映画音楽の要素を大胆にミックスさせようと挑んだのはこの頃から。ストリングス隊が加わっての新しい創作の起点であり、間違いなく転機といえる作品です。
ドラマティックな構成になったというのが第一印象でした。TAKAさんが敬愛するベートーヴェンの誕生日に由来する#1「16.12」に始まり、唯一の被爆国として世界平和を訴える哀切のクロージングトラック#8「A Thousand Paper Cranes」にいたるまで。
自分たちはここにいると痛切に訴えた前作から、人々へ寄り添うエモーショナルな作品へ。静から動への遷移という基本線はありつつも、楽器の音色が増えたことや幾分かの抑制を効かせたことで、作品がビルドアップされています。
特に#3「Halcyon(Beautiful Days)」の存在でしょう。結成当初からの険しい旅路を通して培った色々な経験を通して、初めて書いた歓喜の曲。
ツアーを通して得たたくさんのファンや仲間に対する感謝と希望が、ストリングスと轟音に添えられて響き渡る。当時から20年を超える今に至るまで、ライヴでずっと演奏され続けている重要曲です。
そして、一番の破壊力を持つ15分超の#7「Lost Snow」。それは降り積もる雪の集積がもたらした巨大な大雪山のごとく。MONOは存在も音楽も冬のイメージがあるんですけど、最初に決定付けたのが本曲であると感じています(ジャケットや「Ashes In The Snow」も後押ししてますが)。
冒頭にも書いたとおりにバンドにとって転機といえる作品であり、スタイルが固まった作品とも言えます。Pitchforkを始めとした世界の音楽誌にもレビューが掲載されるようになったり、世界各国をさらに細かくまわるようになる。
結成当初からがむしゃらに進んだ道無き道は、確かなものへと変わっていったのです。
You Are There (2006)
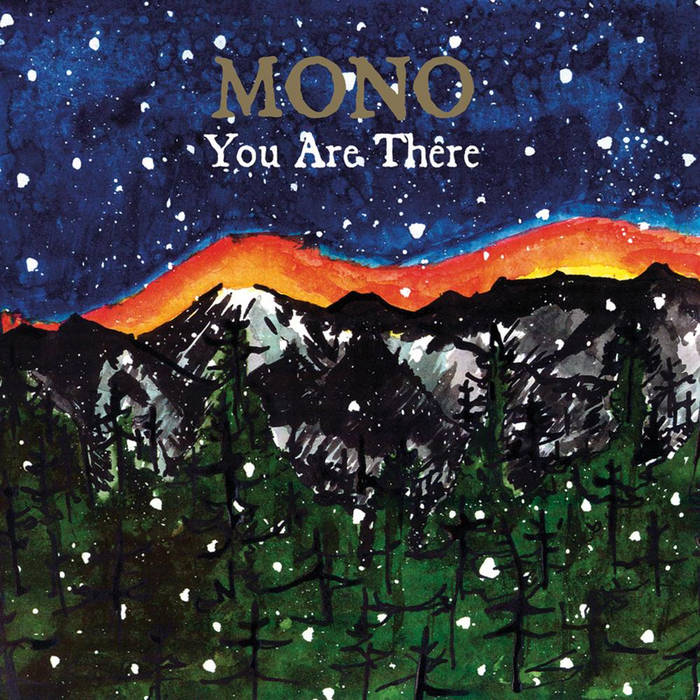
4thアルバム。全6曲約60分収録。前作に引き続いてスティーヴ・アルビニと共に製作。 「”死”と向き合って徹底的に”生”を浮かび上がらせる作品を作った」 とTAKAさんは語ります。
さらにはバンドの成長と共に、創作の原点である映画監督ラース・フォン・トリアーの作品『奇跡の海』に匹敵する壮大なものが今ならできるかもという思いもあったそう。
その結晶が『You Are There』です。全6曲約60分にわたって「生と死」というテーマに真摯に向き合っています。わたし個人の話をすればMONOで最初に聴いたアルバムが本作です。
音楽的には前作からの継続と上積みです。全てが消えて無くなってしまいそうな儚さ、周り全部が闇に包まれたような絶望感、痛みと苦しみを持つ中で生き続けることへの逡巡。これらを抱え込みながらもその重さを希望へと昇華していく。
心のさらに深い部分にまで届くものとなっているのは、一音一音がより繊細になったからか、張り詰める緊張感からか、さらなる臨場感が生まれているからだろうか。
「生と死」をテーマにしていることもあって、全作品中で精神的な部分においての重さを最も感じさせます。
本作においては#3「Yearning」と#6「Moonlight」が特別な存在感を放っています。前者は、MONOの楽曲のなかでわたしが一番好きな曲です(ちなみにベスト3を挙げるなら「The Kidnapper Bell」と「com?」とこの曲)。
孤独に寄り添うようなクリーンギターの音色が鳴り響くも、徐々に音の輪郭を膨らませながら訪れる試練の哀感と打ち付けるような凍てつく音の波動。人間は無力だと突き付けるようなブリザードの波状/連続にいつも圧倒されてしまいます。
そして後者の#6「Moonlight」。ポストロック~インスト・バンドは数多く存在すれど、MONOが日本をルーツにしたバンドであることを裏付ける曲だと感じる壮大な叙情詩です。
ギターのトレモロ、もの悲しいピアノとストリングスのデリケートな共鳴がリードしながら、クライマックスに向けてドラマティックな轟音を持つ展開へとなだれ込む。その美しさたるや彼等がこれまでに発表した中でもトップクラスのものです。
死を迎えることはわたしたち人間にとって不可避であるけれど、MONOの音楽からは生命の灯を再点火させるような崇高さを感じます。生と死の螺旋をくぐりぬけるかのような奇跡的かつ壮絶な世界の体験。
『You Are There』は誰にとっても特別になりうる音楽となっています。
Hymn to the Immortal Wind (2009)

5thアルバム。全7曲約67分収録。スティーヴ・アルビニとの鉄壁のコンビを継続し、『不死の風への賛歌』と題された本作。”ひとりの少年と少女の生と死、魂の永遠性をめぐる、 本作の為に実際に書き下ろされた物語”に基づいて制作され、聴き手に対して明確な映像喚起を促すような作りが成されています。
始まりの#1「Ashes In The Show」から#7「Everlasting Light」までの全7曲67分間。 静から動へとゆるやかに行き交うことで生まれる壮大なスケール感とダイナミズムは健在。
本作ではそこに加わる20人超に及ぶ弦楽オーケストラとの共演がこの物語が持つ説得力や壮麗な美を一段上のベクトルへと押し上げています。前作以上に大所帯となったこと、またクラシック要素がさらに増したことで、荘厳な重みと臨場感が大きく助長されている。
研ぎ澄まされた一音一音が内包する感情は重くて深い。バンドのトレードマークとなった#1「Ashes In The Snow」は猛吹雪の渦中から美しきと歓喜を拾い上げ、優しく労わるように響き渡る#4「Pure As Snow」は魂の底にまで浄化を促すかのよう。 ラストを飾る#7「Everlasting Light」の勇ましい旋律は、希望を持って生きることを力強く祝福する。
救いようの無い絶望感の広がり、それを天へと解放して包み込むような深い慈愛。これを天国と地獄ほどの振り幅で描ききった前作の方が手触りとしては好み。
けれども、絶望・悲しみ・虚無・哀切・怨恨・孤独・憂鬱など幾多に及ぶ負の感情の群れを優しく撫で上げ、今までよりも遥かに圧倒的な美しさに満ちた光に昇華して、無二たる感動を聴き手に届ける本作もまた胸打たれます。
バンド結成10年目の結晶。そして、日本のインストゥルメンタル・バンドとして世界での立ち位置を決定づけた傑作にして重要作。フル・オーケストラとの融合を果たし、クラシックの響きまで備えた崇高でドラマティックなインストゥルメンタルは、あらゆる人種や国境を越えて人々の胸を打ったのです。
Holy Ground(2010)

2009年5月にニューヨークで行われた24人のオーケストラとの10周年記念ライヴを収録したCD+DVDの2枚組。全世界3000枚限定という3枚組アナログ盤+DVDも同時発売となっています。
NYの前衛オーケストラ集団のワードレス・ミュージック・オーケストラを招聘。荘厳かつ優美なオーケストレーションは従来のサウンドに新たな光を灯しており、劇的なダイナミズムを加味しています。
ヴァイオリンやチェロの弦一本一本の共鳴が幽玄で美しい揺らぎを、ティンパニやシンバルなどはリズムにポジティヴな躍動感と歓喜を与えることに成功。多彩な楽器が融合することによって密度濃く繊細に描写されています。
選曲自体は5thアルバム『Hymn to the Immortal WInd』からがメインです。しかし、オーケストラとの共演を見越した相性を重視したのか、ライヴであまり演奏されてこなかった曲も披露。「Are You There?」や「Candles, 1 Wish」は勝手ながらそう思っています。
彼等は3rdアルバム以降、ロックとクラシック音楽の力を結び付けてきました。その融合を初めてステージという場で試みたにも関わらず、大人数でここまで圧倒的な空間を作り上げてしまうとは、恐れ入る。
壮大なサウンドを完璧に封じ込めた録音がまた素晴らしく、迫真的で臨場感のある本作を聴いていると自分が行った東京のオーケストラ公演を思い出します。
音楽の力を頑なに信じ続け、真摯に音楽と向き合い、インストゥルメンタルという方法論で数多の人々に感動を届けてきたMONO。自身の10年の軌跡と想いが本作品にはギッチリと凝縮されています。
For My Parents (2012)

6thアルバム。全5曲約55分収録。3rdアルバムの頃から歩みを共にし、バンドの礎を築いてきたスティーヴ・アルビニのもとを離れ、ヘンリー・ハーシュをプロデューサーに起用しています。
オーケストラとともに鳥肌が立つほどの感動的なステージを繰り広げたFUJIROCK 2012。ワールドプレミアとして本作の3曲が披露されました(わたしも現地にて体感)。
”For My Parents = 両親への愛を込めた”という本作。前述したようにアルビニのもとは離れたとはいえ、継続路線。どこかもの悲しさを湛えた叙情的なクリーン・ギター、大らかなメロディ、大地を踏みしめるリズム、吹き荒ぶ吹雪のような轟音ノイズ。フルオーケストラとバンド・サウンドで聴かせる、劇的でダイナミックなインストゥルメンタルは健在。
過去作と比較すれば、轟音で得られるカタルシスは以前ほどではないかもしれません。それでも丁寧に綴られていくストーリー展開は流石で、一体化したバンド・サウンドとオーケストラが、光と希望の音色を高らかに鳴らしています。
心血を注いで鳴らされる音色のひとつひとつがやがては壮大な音の調べに変わり、荘厳なオーケストレーションともに感情豊かに表現される#1「Legend」。
宮崎駿的な何かを感じずにはいられないスケール感に、哀愁と郷愁の音色が滲む私的な本作のベスト曲#2「Nostalgia」。
そして、張り詰めた緊張感の中で、2部構成のような感じで感動的な物語を刻んでいく#4「Unseen Harbor」。全5曲55分は、映画を思わせる圧倒的なスケールと溢れるドラマティシズムを貫いている。
言葉は持ちませんが言葉以上に雄弁に語り、心の芯に響くサウンド。結成当初から13年かけて培い、追求し、形にしてきたものがここに表れています。
The Last Dawn (2014)

7thアルバム。6曲約48分収録。明暗の極北を描く『The Last Dawn』『Rays of Darkness』の驚きのフルアルバム2枚同時リリース。
ここ2作で特に顕著だったクラシックの色濃いオーケストラ・アレンジが抑えられ、再び4人でのバンド・サウンドに回帰したことが特徴となっています。
まずは”明”をテーマとした全6曲の『The Last Dawn』。悲しみの底辺を綴ったような静パートから究極の歓喜へと向かう動パートへと遷移する#1「The Land Between Tides / Glory」や#3「Cyclone」からして彼等の特徴が表れています。
オーケストラが全面に出ていなくとも、本作はみながイメージするMONOのサウンドが凝縮。あらゆる感情を受け入れながら、最も残酷なところから最も清らかで美しい場所を見出す。力強く光の音楽へと凝縮させていく。
WOWOWの連続ドラマ、角田光代さん原作の”かなたの子”のテーマ曲として書き下ろされた#2「kanata」は、ロングバージョンとして深化を遂げました。
#2と同じくピアノを基調に織り上げていく#4「Elysian Castles」もまた美しい。曲によってはチェロやヴァイオリンが色付けし、ピアノやグロッケンが添えられて叙情性や物語性を研いでいく。
その中で本作では#5「Where We Begin」から#6「The Last Dawn」が光と祈祷の音楽として壮大に鳴り響く。特に#5の後半においての地球の胎動のようなリズムと轟音ギターが奏でる、希望のシンフォニーは感動的。
過去へと回帰しつつ、実にMONOらしい作品。
Rays of Darkness (2014)

8thアルバム。全4曲約35分収録。前述の『The Last Dawn』とは対の”暗”となる作風で、重厚かつ混沌としています。#1「Recoil, Ignite」から驚かされ、「Com(?)」や「Lost Snow」にも匹敵する破壊力と哀切がある。
それほどに本曲は精神的にも肉体的にもズシリとくる重み。leave them all behind 2014で一足先に体感しましたが、とてもダイナミズムを感じさせるものでした。
本作でMONOがこれまでにない暗黒へ聴き手を連れて行っているのは明白で、渦巻く負の感情と荘厳でヘヴィなサウンドスケープが混沌をより深めていく。
#2「Surrender」ではJacob Valenzuela (Calexico)によるトランペットが長閑で優しい空気を運んではいるものの、全体を通すと気分が沈むような暗さ。
envyのヴォーカリストであるTetsuya Fukagawaが参加した#3「The Hands That Holds The Truth」 によるエモーションの放出もひどくヘヴィ。確かに1stや2ndの頃の感触はあれど、ベクトルの違いを感じさせる。
極めつけは#4「The Last Rays」で、SUNN O)))辺りが頭によぎる拷問のようなノイズ・ドローン。まるで絶望のどん底から抜けださせないことを表現しているかのよう。
いずれにしても2枚を通して、ひとつのストーリーが紡がれているのは確かでしょう。充実の2作品。
Requiem for Hell (2016)

9thアルバム。全5曲約46分収録。5thアルバム『Hymn to the Immortal Wind』以来のスティーヴ・アルビニ先生とのタッグが復活しています。マスタリングはボブ・ウェストンが担当。
近年のMONOはオーケストレーションを有効活用しつつ、メンバー4人としてのサウンドを重視しているように思います。2枚同時リリースの前前作と前作はその流れに向かった作品で、光と闇を両極端に描きました。本作ではそれらを巧みに凝縮。
特に闇方面につながるであろう怒り、悲壮感、哀切等の表現がさらにヘヴィであり、洗練と初期衝動の両面が上手く表現されています。
静寂から轟音へ。数々のフォロワーからお手本とされるその手法は、ポストロック最高金賞受賞レベルなわけですが、そこにアルビニ先生による録音の復活で一層の生々しさとダイナミクスを感じさせる仕上がりです。
地獄、煉獄、天国の3編から成るダンテの「神曲」が本作のモチーフになっているようですが、そういった組曲としての構成美があります。
THE OCEANとのスプリットに収録された#1「Death In Reverse」、さらには中核を成す18分超えの大曲#3「Requiem For Hell」が地獄/煉獄編。
これらの曲で登場する猛烈な吹雪のようなギター・ノイズは重々しく心身に迫ります。特に#3はかつての「Yearning」よりも試練のような哀感に溢れ、「Com(?)」よりも大きなエネルギーが爆発。これまでに発表した曲の中で最もアグレッシヴといえる楽曲かもしれません。
オーケストレーションを加えて荘重に作品を彩る#2「Stellar」、#5「The Last Scene」は天国編。#1や#3で地獄への最接近を果たしている分、本作においてはストリングスの鳴らす希望がまばゆいまでに発光します。
それにトレモロが生命の誕生とこれからの成長を祝福するような#4「Ely’s Heartbeat」はひどく感傷を誘う。この曲ではTemporary Residenceのオーナーの子どもの鼓動を使用したそうですが、MONOの真芯そのままの音楽性でプラスアルファの試みも堂に入っています。
アルビニ先生への回帰、そして自らを突き詰めることで『You Are There』よりも儚く重く尊い本作に辿り着いてみせました。彼等はいつだって轟く音とともに天国と地獄を描き、人間の根源を問う。その真骨頂が重々しく表現された1枚。
Nowhere Now Here (2019)

10thアルバム。全10曲約60分収録。結成20周年。結成からオリジナルメンバーでずっとやってきた4人組から、ドラムのTakadaさんが脱退。さらにはマネージメント会社との大きなトラブル。
音楽でのことも音楽外のことでも問題を抱え、百戦錬磨のバンドでも”解散寸前”と自ら吐露するぐらいに、先が見えない事態に置かれてしまっていたようです。
そこからアメリカ人ドラマーである・Dahm氏が加入。上記のマネージメント問題の解消。「夜明けの前のダークネス」とTAKAさんは語っていましたが、絶望的な状況を経て新しい地平へとバンドは踏み出しました。
怒りを吐き出せ。音に震えろ。漲るアングリー精神、心から血を流さざるを得ないノイズ大嵐#2「After You Comes The Flood」が本作を受け止める覚悟を問います。
出発点は怒り。辿り着くは、”Now Here = 今、ここに”の証明。結成20年10枚目だからといって集大成のようなものを完成させたわけではありません。
バンドが背負ってしまった感情の大きな揺れ動きを作品に投影し、20年目にして初めて引き抜く武器であるTamakiさん歌入りの曲#3「Breathe」を披露する。でも、まぎれもなく今のMONOの音です。
いつも通りに多数の弦楽隊が参加していても、祈りや希望といった光性よりも暗性の色味と感情の方が強い。本作を象徴する怒りであり、険しい現状を乗り越える決意と打破への助力となってストリングスは鳴り響きます。
暗鬱の最果てから今と未来を勇壮に邁進していく表題曲#4「Nowhere, Now Here」はその象徴。#8「Meet Us Where the Night Ends」にしても人間のうちにある最深部の闇をかき消すように音は轟く。
ここまでMONOが、自身が抱いたパーソナルな感情を作品に反映させたのは初です。その生々しさは、盟友スティーヴ・アルビニとの一発録りによって、さらに力強さを増しています。キレイに着飾ったものに意味はない、トリミングされたものに真の美しさはない。生身だけの音が全てを物語り、これからを創り上げる。
アニバーサリーだからといって祝福するような作品ではなく、いつものように他者を慈しむものでもありません。ここ数年の不遇を自分達の音楽に変え、自らを肯定する。自らを救済する。
本作が残したものは苦闘の痕かもしれませんが、それを誰かにとっての人生を射抜く音、救う音にまで昇華してしまう辺り、MONOとしての凄みであることを実感します。
Beyond The Past(2021)

2019年12月14日にイギリスのBarbican Hallで行われた、活動20周年を締めくくるオーケストラを率いた公演“Beyond the Past”を収録したCD2枚組/LP3枚組のライブ作品。
全12曲で約2時間にも及ぶ記念碑には、NME誌にて”This Is Music For The Gods__神の音楽”と賞賛された理由が詰まっています。
わたし自身、MONOのオーケストラ公演は2度体感しています。最初が2009年12月に渋谷O-EASTで行われた10周年記念公演。2度目は2012年のフジロックにて。そんな記憶がよみがえってくる本作です。
公演の主軸となっているのは、2019年初頭に発表された10枚目のフルアルバム『Nowhere Now Here』であり、そこから5曲。またライヴ当時に最新曲であったA.A. Williamsとのコラボ曲『Exit in Darkness』も含まれます。
そしてHalcyon (Beautiful Days)」や「Ashes in the Snow」といったバンドの顔といえる定番/名曲も演奏。全アルバムからというわけではないですが、初期の「Com(?)」も含めて20年という歴史を感じさせる12曲を披露しています。
冒頭を飾る#1「God Bless」~「After You Comes the Flood」で雷鳴のような音が轟き、その迫力と臨場感に気圧される。MONOのライヴの醍醐味が早くもといったところでしょうか。ひとつの大きな物語を狂おしく繊細な表現で紡いでいく。心血を注いで音を研ぎ澄ます。
MONOの音楽は、心の最も深い部分に届くものだと私自身感じていますが、過剰なまでに感情を左右する音の結晶体は、オーケストラと組み合わさることでそれはさらに増幅します。
オーケストラの音はあくまで補助的に聴こえるものの、ベースのTamakiさんが歌声を披露する「Breathe」ではギターに折り重なる弦楽隊の音色が揺らぎと厚みをもたらしています。
悲壮感や怒りを内包しつつ壮大な音の波に飲み込まれていく「Nowhere Now Here」にしても壮絶というほかありません。
バンドのシンボルともいえる「Halcyon」や「Ashes In The Snow」が本編終盤にて祝祭と凍てつく波動をもたらす中で、やはり一番インパクトがあるのは、アンコールにてラストを飾った「Com(?)」でしょうか。私的にモグワイの「My Father My King」と比肩するほどの轟きがある16分超の曲です。
終盤にいくにつれてオーケストラ関係ねえと言わんばかりに猛嵐の如きノイズが埋め尽くす様は圧巻。身も心も粉々するような、真っ白な世界に身を置くことになります。
MONOはインスト・バンドは居場所がなかったという90年代後半から活動を始め、海外から切り拓くことで活路を見出してきた人たちです。
20年にも及ぶ活動で想像を絶するほどの困難に直面しては乗り越え、海外2000人規模のホールにて聴衆を魅了する。
真摯に誠実に表現を突き詰めてきたことでの集大成。彼らが成し遂げてきたことの偉大さにただただ敬服します。
Pilgrimage of the Soul (2021)

11thアルバム。全8曲約57分収録。”Pilgrimage of the Soul = 魂の巡礼” こちらのインタビュー動画にて語られてますが、MONO自身が紡いできた20年の歴史を音で描いたものとなっています。
もちろん、スティーヴ・アルビニとのコンビにて、COVID-19が猛威をふるった2020年夏に制作。
1999年結成当初、日本ではインスト・バンドゆえに居場所が無かった。そのため海外に求めるも最初のアメリカでの公演はたった5~6人。どん底のスタートから世界が認める存在へ。その歴史の追体験。
ありったけのF●●K YOU元気玉ともいうべき前作収録「After You Comes The Flood」とはまた別の炸裂感を放つ#1「Riptide」がオープナー。80秒の静寂を経てベース音を合図にマシンガンのごとく乱れ打つドラム、悲壮感たっぷりに掻き鳴らすギターが暴れ回る。本作中で最も重く激しい一撃であり、困難で険しい旅の始まりだったことを物語ります。
逆境を乗り越えようとスタートを切ると、エピックな叙事詩として優美な側面がフォーカスされていく。旋回する電子音と心地よいビートを用いた#2「Imperfect Things」で驚かし、内省と瞑想の渦中へ放り込む#3「Heaven In A Wild Flower」が穏やかに染みわたっていきます。
純真な心は何よりも強いと説く#5「Innocence」がもたらす光と祝福のダイナミクスは、近作では感じえなかったものです。
前作は怒りを出発点に存続の危機から、反骨心に満ちた存在証明を掻き鳴らしました。本作はもっと和らいだものとなっており、映画音楽的なドラマ性やリリシズムが戻っています。そして、溢れんばかりの喜怒哀楽。
自身が辿ってきたプロセスがたくさんの感情と結びつき、自らを顧みては祝福し、音楽を通して聴き手と感情を分かち合います。
12分超と最も長い#7「Hold Infinity In The Palm Of Your Hand」は、MONOの歴史の凝縮と呼べる曲です。グロッケンシュピールを用いていること、大きな起伏と過度なロマンティックさを湛えたサウンド。
それは代表曲「Ahses In The Snow」の幽玄な美しさに並ぼうとするものに感じます。魂の深奥にまで染み入るその音は、聴く者の精神を掻き立てると同時に深く浄化するものです。
「個人的な体験が最も創造的なことである」というマーティン・スコセッシの言葉がありますが、本作はそれにふさわしい作品だと思います。MONOは20年もの間、毎年100本を超えるライヴと総計59カ国を旅してきました。
その巡礼と軌跡の断片を通して共有し合う壮麗なる結晶体。穏やかなピアノ伴奏とともに締めくくる#8「And Eternity in an Hour」が描くのは、バンドにとっても世界にとっても美しい未来だとわたしは信じたい。
OATH(2024)

12thアルバム。全11曲約71分収録。バンド結成25周年を飾る作品。2024年5月に急逝したスティーヴ・アルビニとタッグを組んだ最後のオリジナルアルバムとなりました(クリスマス時期にリリースしているEPシリーズと来年公開予定の映画のサントラを24年4月に彼と録音しており、厳密に最後ではない)。
”『OATH』はこれまで僕たちがリリースしたどのアルバムとも違う世界だと感じています。これまで僕たちが表現してきた怒りや、暗闇、絶望、悲しみの感情は全くなく、自分が持っていないものや、理不尽なことに対しての不満ではなく、既に自分達に与えられている豊かさにフォーカスしたアルバムになりました(Belongのインタビューより)”。
ようするに当たり前の生活を送れる尊さにもっと目を向けること。今、生きているこの瞬間に感謝すること。発言にもある通りに悲壮感や怒りといった負の感情で膨れ上がる大音量はなく、作品に漂うのは大らかさや懐の深さ。もっといえば愛です。ゆえにMONOの全カタログの中で最も光と神聖さに溢れています。
フルオーケストラを携え、クラシックとバンド音楽を密に融合する手法を研ぎ澄ませる。そこに調和された音楽としての豊かさを感じさせますが、これまで以上に穏やかで優雅な演奏が際立ちます。
また制作について”映画や小説のような70分のストーリー仕立てになっている。このアルバムは1年かけて作曲。春から始まり、夏、秋、冬と、その時々に感じたことを書き綴った(SOUNDS VEGANのインタビュー)”と回答。
#1「Us, Then」では近親者の死を始め、大切な人たちへの弔いをシンセのフレーズに託しており、これが終曲#11「Time Goes By」まで繰り返し登場します。そのモチーフは死は決して断絶ではなく、人々の記憶の中で生き続けることを示唆する。
アルバムのリードトラック#4「Run On」では控えめな電子音の装飾と地球の鼓動を思わせるリズムの上をツインギターとストリングスが重なり、希望を高らかに鳴らしてます。そして終盤を飾る#10「We All Shine On」。MONOの王道を踏襲するスタイルではありますが、終盤でフルオーケストラを引き連れて起こす爆発には、それこそ前述のインタビュー内で自身の音を表現した”The Noise of Joy=歓喜のノイズ”が誰しもに等しく降り注ぐ。
悲しみと喜び、光と闇、生と死。長きにわたって対極の二面性を追求してきたバンドですが、辿り着いたのは万物に対する慈愛。そしてMONOが25年にわたって信じ続けた美や希望が『OATH』にあります。
どれを聴く?
聴いてみたいと思ったけど、どれから聴けばいいの?
以下にオススメ3作品をあげました。
NME誌にて”神の音楽”と形容されたその真髄を堪能できるはずです。
MONOの音楽を巡礼するプレイリスト
わたしなりにMONOを知るためのプレイリストをつくってみました。
全7曲、ぜひ聴いてみてください。














