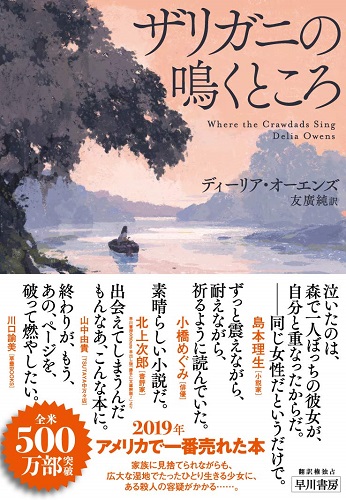
約500ページに及ぶ大作。上記にある通りに2021年の本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞した一作です。執筆者は、ノンフィクションの共著を3冊出版している動物学者ディーリア・オーエンズ氏。彼女が70歳近くに初めて敢行した小説が本著となります。その事実だけでも驚き。日本にも63歳にして『おらおらでひとりいぐも』で文藝新人賞と芥川賞をW受賞した若竹千佐子さんという方もいますけど。
物語は非情なまでにムゴいです。DV父による影響で、小学生手前ぐらいの幼き少女・カイアだけを家族は置き去りにしていくわけですから(父も行方不明になる)。その年齢でひとりで生きていかざるを得ない現実。遠のいた輝かしい未来。湿地から見渡す限り拡がる自然は、絶望を乱反射しているかのように最初は映る。それでも根源的に備わる人間の生存本能が、生きるを駆り立てます。カイアは湿地の自然に守られる中で、電気なしでトウモロコシの粥を食べて生きるのがやっと生活を送る。
作品の主な時代背景が1950年代~1960年代。舞台はアメリカですが、架空の村として描かれているバークリー・コーブ。主人公のカイアが活きる湿地に関しては、”ディズマル湿地をモデルにしていると思われる“と訳者あとがきにて書かれています。
ちなみに”ザリガニの鳴くところ”とは。本著では「茂みの奥深く、生き物たちが自然のままで生きてる場所(p155)」と書かれている。
本作からは、昨年に映画鑑賞した『異端の鳥』を思い出す部分がある。あちらはヨーロッパが舞台で10歳少年の物語。ですが時代はわりと近い。ホロコーストから逃れるために疎開したものの、人々から疎外されて時には奴隷のように扱われる。ひとりで常に死を間近に感じた中で生きていく。地獄巡りのごとき、毎日違う苦しみと悲劇が襲ってくる状況なのに。負の衆愚詰め放題パックのごとき残酷描写は、今でも脳裏にこびりついています。
孤独、疎外、差別。両作品に通底するテーマ。ただ、『ザリガニの鳴くところ』は少女の成長譚としてのカタルシスがあります。大自然と生物たちとの共生、孤独の中でサバイブするたくましき生き様。その中で関わる人間は少ないながらも、手を差しのべる黒人夫婦、言葉・文学を教えてくれた初恋相手となるテイト。彼等を通して人が人を求める理由、人が人を通して影響し合うことの大切さ、それを教えてくれます。
けれども、再び起こってしまった裏切りに近い別れが、彼女をまた苦しめる。途中からはミステリー要素を帯びながら、話は展開。カイアが社会から受ける差別・疎外問題が深刻化していく中で、彼女自身が問う生きる意味。動物学者である著者の自然と動物描写、効果的に配置される詩は物語を雄弁に彩る中、なお強い気持ちを持って生き続けるカイアの姿に胸打たれる。
全ての生きるを鼓舞し、肯定してくれる。そんな小説が読みたいあなたに。


