轟音ポストロック30選 21-30
Jakob / Solace(2006)

1998年にニュージーランドで結成された3人組。公式サイトによると本業の仕事を持ちながら、24年を超えて今も活動を続けていて5枚の作品を残している。本作は3rdアルバム。
織物職人のごとき慎重なタッチでテクスチャーを構築し続けるインストであり、派手さはない。
メンバー3人とも攻撃と守備のリスク管理に長けたボランチのようで、催眠を誘うミニマルなギターから地響きを起こす重厚な音壁までサウンドを統制。
完全にリミットを外れてNadjaばりの音量が鼓膜を襲う#2「Pneumonic」、彼等なりの轟音ポストロックの極地#5「Safety In Numbers」などバンドの実力を思い知る。そしてJakobの音楽は”祈り”という言葉が不思議と似合う。
オススメ曲:#2「Pneumonic」

Laura / Radio Swan Is Down(2006)

2001年にオーストラリア・メルボルンで結成された6人組。本作は2ndアルバムで当時に国内盤も発売された。チェロやグロッケンシュピールを加えた編成に電子音を含めて色合いを増やし、繊細な情緒を表現。
前半はGY!BE辺りを彷彿とさせる暗い旅路を進み、後半にかけては穏やかに希望をふくらませていくが、心地良さよりも侘しさが通底している。
一部の曲で声を楽器のように用い、ギターとチェロが物悲しく共鳴。鎮静と暴発が繰り返される音像に言葉は無いが、人生の苦みと喜びを嚙みしめる文学性が感じられる。
オススメ曲:#3「I Hope」
Pijn / From Low Beams Of Hope(2024)
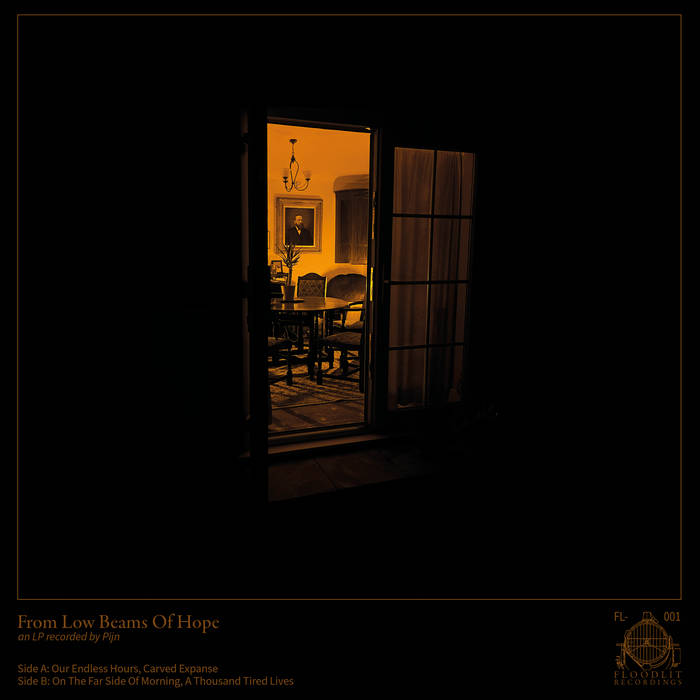
UKマンチェスターを拠点に2016年から活動するバンド。”カタルシス溢れるヘヴィなポストロック”と自身で名乗り、バンド名はオランダ語で”痛み”を意味する(英語だとPainと同義語)。
本作は6年ぶりのフルアルバムとなる2nd。音楽的にはポストロック~ポストメタル間を揺れ動くような作風である。そのヘヴィなポストロック/ポストメタルを下地にオーケストレーション要素を強化しており、ストリングスやホーン、ピアノが美しく調和。
感情の浮き沈みや人生の起伏を長尺の中で雄弁に表現しており、以前よりもThee Silver Mt. ZionやDo Make Say Thinkっぽいと感じる場面が増えた。
内省と葛藤を課しながら希望へと向かう本作は1曲平均11分を数える4つの長編曲で構成。多楽器による重奏はこれまで以上に躍動感と歓喜を運んでくる。全体から受ける印象を言えば、タイトルの少ない希望の光とは相反するポジティブさ。
オススメ曲:#3「On The Far Side Of Morning」
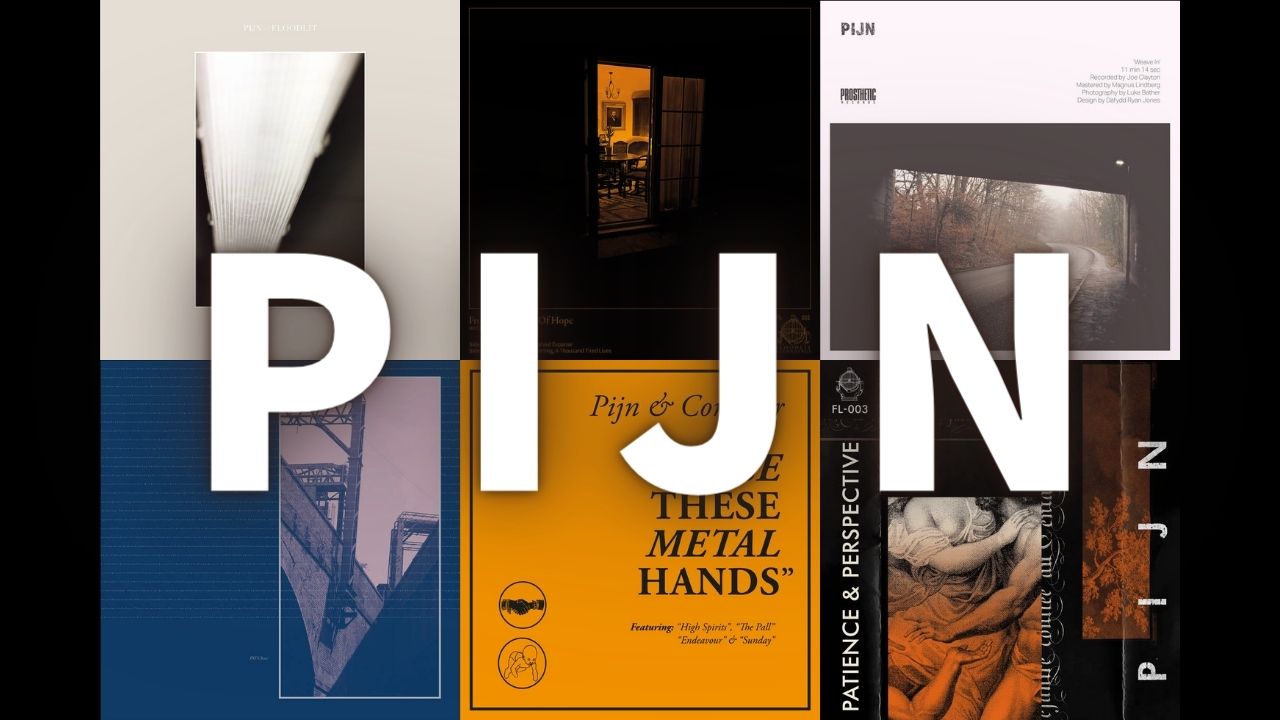
Audrey Fall / Mitau(2014)

ラトビア共和国を拠点に活動したインストゥルメンタル・カルテットの唯一のフルアルバム。
静から動への王道パターンに加え、#5「Bermondt」の重厚なリフの応酬はRussian Circlesを思わせ、マスロック~プログレの理知的な構成が取られた曲もあり。
美しいツインギターの染み入るように広がっていく一大叙情詩#6「Valdeka」は感動的であり、優美なアンビエンスをくぐり抜けた先に轟音プログレッシヴの大河に突入する#8「Courland Aa」もシビれる楽曲。
ポストロックとポストメタルの中間的な強度と叙情性を誇りながらも、全体を通して美しい物語を描いている。
オススメ曲:#3「Wolmar」

Lost in Kiev / Nuit Noire(2016)

2007年から活動するフランス・パリのインスト4人組の2ndアルバム。リリースはDunk!Recordsより。マスタリングをCult of LunaのMagnus Lindbergが担当。
”ポストロックのメランコリックな瞬間とポストハードコアのヘビーさをミックスした“という自身の持ち味を以前にIDIOTEQのインタビューで語る。本記事に相当する轟音系に属すポストロックだが、彼等の場合はサンプリングではなく俳優を起用してセリフのパートを録音しているのが特徴。
”映画的なポストロック”を強調し、サントラというよりもドラマ/映画のワンシーンをつくり出しているような感覚に近い。聴き手が音から映像を想像して嗜む、そんな効能をもたらすことができるのがLost in Kievの良さ。
また本作はコンセプトは”夜の賛歌”とのことで、夜を徹底的にコンセプチュアルにつづることでバンドの真価を発揮した一作となっている。
オススメ曲:#2「Insomnia」

Oh Hiroshima / In Silence We Yearn(2015)

スウェーデンのクリスティーネハムンを拠点としたポストロック・デュオの2ndアルバム(本作リリース時は4人組)。ヴォーカルやギター、メインコンポーザーを務める兄のJakob Hemström、ドラムや映像関係を担当する弟のOskar Nilssonから成る。
美麗なる轟音インストゥルメンタルという基本形に持つバンドだが、本作から歌ものポストロックとしての側面が強まる。全6曲中5曲で歌入りで、ファルセット等はあまり用いずに中域で穏やかに歌い上げており、シガーロスではなくアルバム・リーフやepic45寄り。
繊細なタッチと轟音をスムーズに連携した美しいストーリーが根幹にあり、特に#2「Mirage」はヴォーカルの入れ方も含めて進化を示した楽曲。さらには#4「Holding Rivers」や#5「Aria」にはチェロ奏者のEllen Hemström(Jakobの妻)が参加し、ドラマティックなスタイルに一段と華を添えている。
Oh Hiroshimaはこれ以降の作品ではより歌もの志向が強まっている。またバンドは完全に兄弟デュオ編成へと移行した。
オススメ曲:#4「Holding Rivers」

If These Trees Could Talk / The Bones Of A Dying World (2016)

アメリカ・オハイオの5人組による3rdアルバム。Metal Blade Recordsからのリリースであることに驚かされるが、トリプルギターを擁した美と重の共演はポストロック~ポストメタルの中間といえるもの。
クリーン・トーン~トレモロのコンビネーションを中心に組み立てられ、全体通しては漂白された白とメランコリックな息遣いの方が勝る。
メタル指数が少し高まった#8「Berlin」のような曲もあるが、一瞬の爆発力にかけるではなく、しなやかにドラマを編んでいく姿勢がこのバンドらしい。
オススメ曲:#1「Solstice」
➡ If These Trees Could Talkの作品紹介はこちら
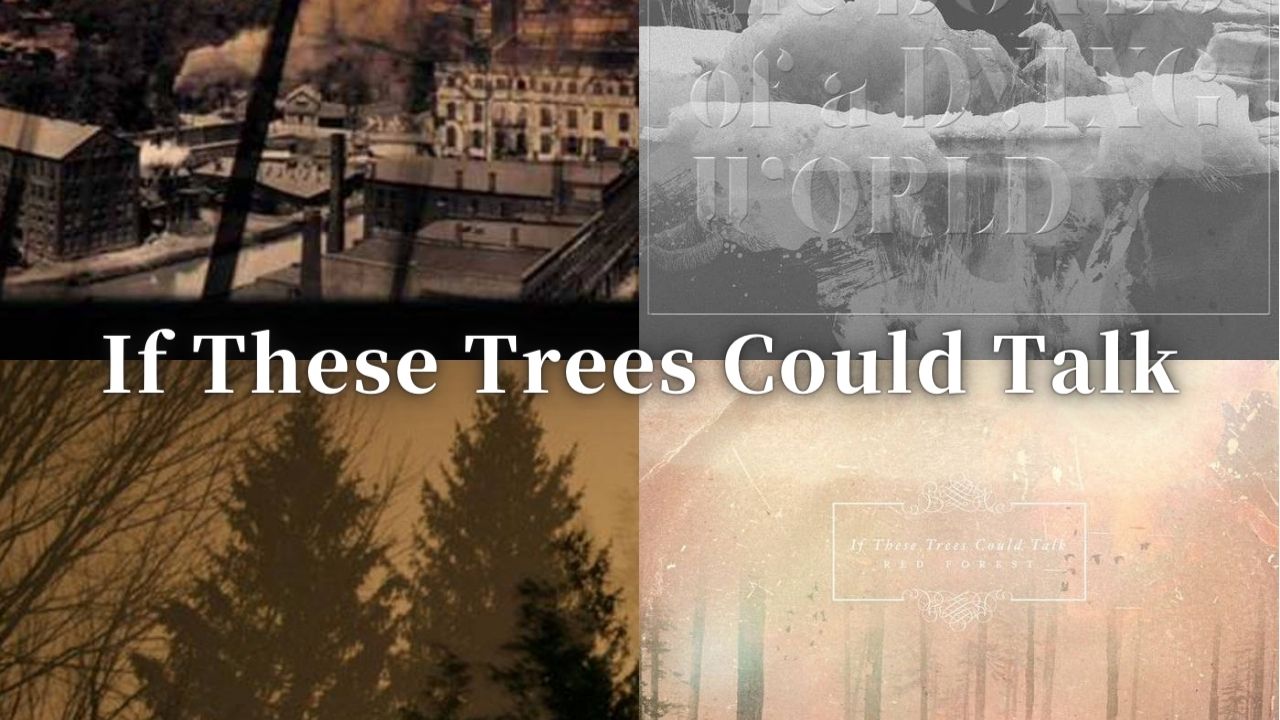
Lost Coast / Lost Coast(2020)

オーストラリア・キャンベラ出身のインスト・ポストロック5人組。2024年4月には念願だったという初来日を果たした彼等は、今となっては珍しいド直球なまでの轟音系ポストロックを奏でます。
アルペジオやトレモロリフを多用するトリプルギターを擁し、静から動へのダイナミクスを丁寧な演奏と共に届ける。しんみりとするギターフレーズを重ねながらメランコリックな波紋と音圧を高めていく#1「2B」に始まり、少し速めのテンポを主体に澄んだ音色が光の世界を創出していく#9「David」まで。
5分~12分台とそろう長尺の中で、轟音系といわれるお約束を律儀にこなしながら、気づけば没頭してしまう物語が展開されている。メンバー5人による生演奏以外のギミックをあまり用いていない点は、Lost Coastの実直さの表れ。
聴いているとExplosions In The Skyや初期This Will Desroy You、そしてMONOといった名前が浮かぶ人は多いはず。己のスタイルを信じ、真摯な姿勢で音楽と向き合い続けた結果が美徳ある本作に表れている。
オススメ曲:#9「David」
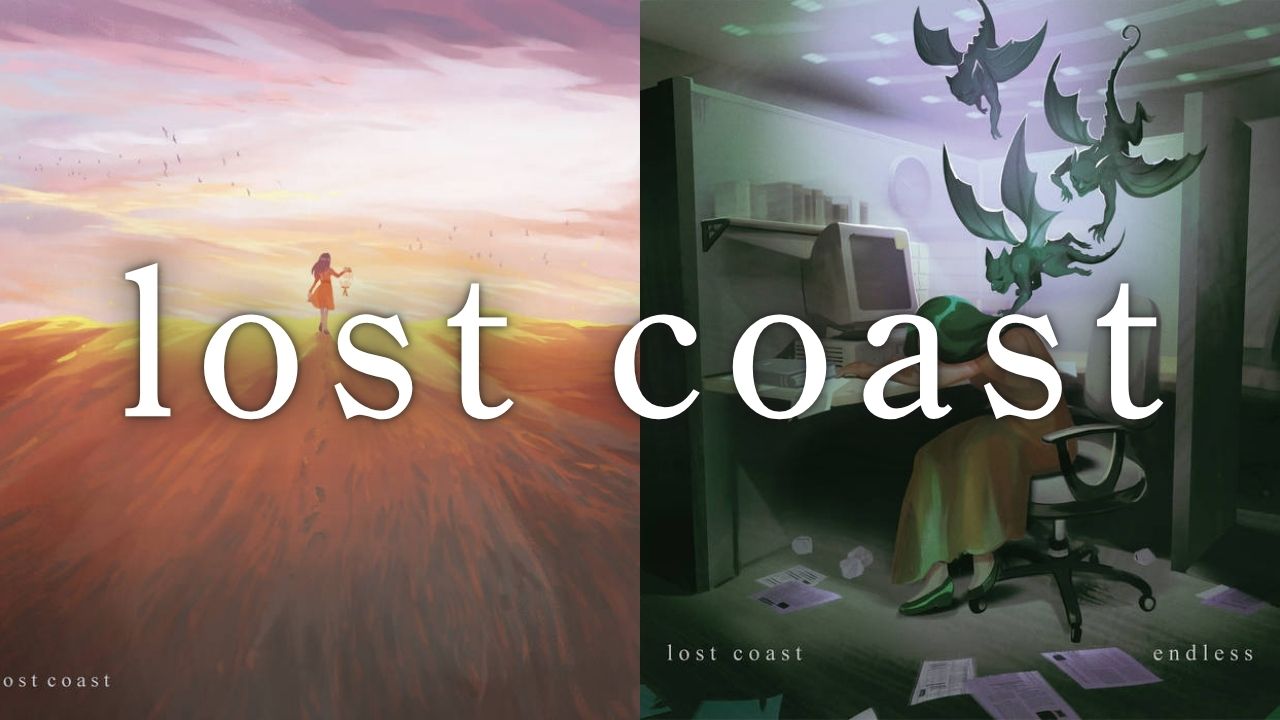
Sleepmakeswaves / Love of Cartography (2014)

オーストラリア・シドニーの4人組。本作は2ndアルバム。今回は挙げていない65daysofstaticを参照しながらもメタル~プログレの強度でビルドアップした、ユーモアと快楽のインストゥルメンタル。
力強いバンドサウンドとネオンのごとき光の帯が広がり、ダンサブルな要素が多く盛り込まれている。少しだけ暗さを感じるシーンもあるが、繊細な音の陶酔感に誘うよりも、昼間だろうと真夜中だろうと関係なく活発なエネルギーでノせてくる。
ポストロックはヒューマンドラマに近いと思っているが、彼等はアクション映画のよう。それこそ”クラブでかけよう轟音ポストロック”みたいな標語が似合う感じ。ちなみに次作は少し控えめでプログレ寄り。
オススメ曲:#9「Something Like Avalanches」

We Lost The Sea / Departure Songs (2015)

オーストラリア・シドニーの6人組による3rdアルバム。ヴォーカリストが2013年に亡くなったことで、本作からインスト・バンドとして再出発した。
静から動へ。先人が生み出したポストロック王道方式を用いて、喪失から再生への物語を気高く美しく描く。
美しいテクスチャーと荘厳なコーラスが重なる31「A Gallant Gentleman」による鎮魂から、Cult of Lunaの影響下にあることを伺わせる「Challenger Part 1~Part2」の30分を超える激動まで。
アルバムに流れるもの悲しいトーンに心を締め付けられるも、放たれる轟音はすべてを包み込む。
オススメ曲:#1「A Gallant Gentleman」











