
スペイン・コルドバ発のポストハードコア・バンド4人組。 ポストハードコアを根幹にし、静と動のコンビネーションを生かした構成、スペイン語による独特の語感を武器としたサウンドを構築。
これまでに4枚のフルアルバムをリリースし、Primavera Sound、Fluff Fest、ArcTanGentなどのヨーロッパの重要フェスに出演するなどの快進撃を果たしています。日本にも2017年5月に来日経験があり。Tokyo Jupiter Recordsから5作品をリリースしています。
本記事はオリジナルアルバム4作品と初期音源集の計5作品について書いています。
アルバム紹介
Viva Belgrado(2013)

スペイン・コルドバ発の若きポストハードコア・バンドの初のフィジカル・リリース作品。完全新曲となる#1, #12、初のレコーディング作品となった「Demo 2012」の#2~#6、EPにあたる『El Invierno』の#7~#11を収録した編集盤となっています。
いかにもTokyo Jupiter Recordsらしいエモーションとメロディの美しさを備えたバンドだなあという印象もあれど、スペイン語の独特の語感が鼓膜にこびりつく感覚に、今までにない新鮮さを覚えます。
キレイめで清涼感あるポストロックから、Touche Amoreっぽい激情系ハードコア等をベースに置いていると感じますが、その激情が渦を巻くサウンドは強烈。
ミッドテンポの楽曲に比重を置いた作りで、美麗なメロディを核にして鮮やかに空間描写を施し、意識的に語りと叫びを交えながら切迫とした昂揚感を生み出しています。そういった点からGantzやSuis La Luneっぽい清流と激流に飲み込まれたり。新曲である#12なんかは、1stの頃のThe Black Heart Rebellionが蘇る様な感触です。
楽曲は静を基調にじわりじわりと盛り上げていくものが多いが、程よくコンパクト(3~4分台の曲が多く、1曲だけ6分の曲がある)。
しかしながら、胸に訴えかける様なエモーションとドラマ性に彩られています。それに前述したように編集盤という特性もあって、作品を聴き進めるごとに感じる洗練もまた頼もしい。
Flores, Carne(2014)
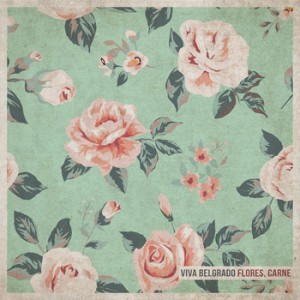
前年にリリースしたセルフタイトルの編集盤からついに1stアルバムを発売。ポストハードコアを根幹にし、静と動のコンビネーションを生かした構成、スペイン語による独特の語感を武器にコルドバから少しずつ進撃を始めている。
冒頭の#1「Báltica」から空間を覆うような美轟音ギターが掻き鳴らされ、ヴォーカルがポエトリーとスクリームを駆使しながら絶対的な昂揚感をもたらしており、envyの「擦り切れた踵と繋いだ手」に近い雰囲気を個人的には感じる曲です。続く#2「De Carne y Flor」は、激情ハードコアの切迫感を突きつけながらもドラマティックに展開。
この後の楽曲にしても叙情性が強化されているのを明確に感じさせます。編集盤の時はアンダーグラウンドな薫りを漂わせ、Funeral Diner辺りの暗鬱さが前に出ていた印象でした。
しかし、本作では一層強まったポストロック/シューゲイザーの要素が、ジャケットの花のように彼等の音楽に彩りを与えています。
繊細なアコギとマーチング風ドラムが牧歌的な空気を持ち込むインスト#5「Los Olivos」の喉越しの良さはなかなかだし、#8「La Reina Pálida」~#9「Osario」という終盤の流れは艶やかな展開の中で蒼い炎のような情熱を放ち、爆発します。
全体を通してアップテンポで攻めることは控えめで、ミッドテンポの丁寧な組立から切実なメッセージをぶつけて感情を刺激。美轟音ポストロック・テイストの効いた#10「Córdoba, 2014」での締めくくりも滋味深いもの。
コンパクトな尺で統一しながらも、スペイン・コルドバのリトルenvyとしての存在感を放つ本作。今後は、コルドバの歴史的建造物であるカラオーラの塔のように巨大な存在へとのし上がって行って欲しいものです。
Ulises(2016)

約1年8ヶ月ぶりとなる2ndフルアルバム。リリースはTokyo Jupiter Recordsからで、節目となる品番”TJP-50″を飾っているのは大きな期待からでしょう。
1stアルバム発表以降にPrimavera Sound、Fluff Fest、ArcTanGentなどのヨーロッパの重要フェスに出演するなどの快進撃で、夢のステップアップを順調に果たしています。
コルドバのリトルenvyと言ってしまった前作と同様に、鮮烈な瞬間を焼き付けるようなドラマティックな楽曲が多め。
体中から迸るほどに情熱的なエネルギーが発露する#2「Pleiades~」や#5「Erida」では焦燥を抱えてぶっちぎる疾走をし、大人びた哀愁をにじませるメロディアスなミッドチューン#3「Por La Manana~」に#9「Apaga La Llum」で心をほろっとさせます。
作品全体を通した緩急のつけかた、それに伴った流れの良さは前作を踏まえた成長と言えるでしょう。クリーントーンやトレモロなどギターは以前にもまして艶やかな陽性の響きを加え、リズム隊はパワフルな躍動感を増してる。
捲し立てるようにスペイン語で叫ぶヴォーカルは、喉仏が擦り切れるんじゃないかってぐらいの懸命さ。自身のスタイルを堅持したまま、それぞれがブラッシュアップを施しています。
力技なんかじゃない洗練されたスマートな聴かせ方ができるようになったとも感じますが、裸のまま剥き出しにした想いを音と声でストレートにぶつける姿勢は変わってません。バンドの持ち味が全て凝縮した#1「Calathea」はキャリア屈指の曲に仕上がっています。
ラストを飾る#11「Ravenala」ではDeafheavenイズムが浸透したポストハードコア+シューゲイズで作品を締めくくる。情熱の国なんて言葉抜きにこのエモ・メイカーぶりがもたらす熱量、ライヴだとなおさらスゴそう。
Bellavista (2020)

約3年8か月ぶりの3rdアルバム。間の2017年5月にはSuis La Luneと共に初来日公演を経験しています。
それがあったからなのでしょう、曲名に「Más Triste que Shinji Ikari(碇シンジ)」や「Ikebukuro Sunshine(池袋サンシャイン)」があり、おそらく日本語が用いられた「Shibari Emocional」という曲もあります。
”コルドバのリトルenvy”と勝手に表現しましたが、その進行方向は本作で多分岐しています。アプローチの基点は激情系ポストハードコアは変わりません。
冒頭の#1「Una Soga」は今までの持ち味を発揮したあいさつ代わりの1曲ですし、緩急を生かしつつ激情系と呼ばれる所以の熱気と精神性を持つ#8「Shbari Emocional」を放ちます。
#5「Un Collar」もこのタイプに属すenvyズムに漬かった曲ではありますが、中盤にスパニッシュ・ギターとフラメンコ要素が取り入れられて、ただ単にこれまでをなぞっているだけではない変化を聴かせます。
タイトルトラック#2「Bellavista」はより顕著です。軽やかなリズム、ギター、歌のコンビネーションを巧みに操り、サビは開放感たっぷりに一緒に歌えるような仕様。
ローファイヒップホップ的#4「Más Triste que Shinji Ikari」、 ダンサブルなリズムの上をスペイン語で忙しなく言葉を重ねる「Ikebukuro Sunshine」も変化を示しており、どこにワープしたかと思うぐらいバンドの表現は飛びます。リッキー・ルビオのパスぐらいトリッキー。
他にも突発的なアコギの導入、アトモスフェリックな音響、マスロックっぽいアプローチもあります。ですが、今までの経験値の上で繰り出しているものだから違和感は無い。
むしろこの野心があるあらこそ、全編を通した開放感のあるつくりに繋がっています。歓迎すべき変化だと思うし、これこそがジャンルの領域を押し広げることに繋がるはずです。
Cancionero de los Cielos(2024)

4thアルバム。全12曲約38分収録。4年の間にギタリストが1名交代。タイトルは”天空の歌集”という意であり、アルバムのコンセプトは空です。このアイデアについてROCKZONEのインタビューでこう答えている。
“ウクライナ生まれの作家 エドアルド・リモノフの著書『The Book of Water』のアイデアをコピーしようとした。この本では彼の人生の全く異なる事柄について語る共通の糸として【水】を取り上げている。雨、湖、サウナ、シャワーを使って、共通点のない様々な物語を語っている。私たちのこのアルバムではどの要素が抽出できるか考えた時、【空】が多くのアイデアを示しているように思えた“
前作からポストハードコアを基盤にバリエーション強化を図っていますが、本作も同様。エレクトロニックやヒップホップの含有、ギターレスの楽曲やラテン調のリズムサポートなどを施しています。さらにはコラボレーションの多さが新境地として待ち構える。
それらを特に感じさせるのが#9「Jupiter And Beyond The Infinite」。Erik Uranoのラップをフィーチャーするのと同時に終盤では子どもたちの合唱コーラスが入ってきます。
また本作から先行公開曲第1弾となった#7「Elena Observando la Osa Mayor」は、ギターレスのエレクトロニック調を貫いた簡素な音像につぶやくようなヴォーカルが乗る。しかもタイトルで遠距離中の彼女の名前を刻む。”テラスで北斗七星を探す君に会えなかったら?“という詞を含めてVivaな衝撃があります。
お約束を繰り返さないバンドとしてアイデアを投下する一方で、十八番のポストハードコアで目が覚めるようなエキサイティングな旅の用意はできている。まくし立てるようなスペイン語詞が強烈な#2「 Chéjov y las Gaviotas」、即効性と熱量の高い#6「Gemini」はそれに該当するでしょう。これまで自身で紡いできたハードコアの糸は決して切れていない。
本作には前作とは違って日本語のタイトルは含まれていませんが、#11「Perfect Blue」は今敏監督による1997年の同名アニメ映画にオマージュされたもの。青空を突き抜けるシューゲイザー・サウンドの上に”あのアニメをもう一度一緒に見る もう一度だけ君と 空も体もパーフェクト・ブルー“と歌う屈指の名曲であり、アルバムのとっかかりにまずこの曲を聴いてみてほしいものです。
前作と比べてもよりオープンなロックアルバムとして懐の深さとアイデアの多さに本作は支えられています。示されているのはオルタナティヴである姿勢。と同時に自分達の経験や感じた事についてしか書かないという真実性を帯びた歌詞がまた刺さる。
特に#1「Vernissage」の詞。彼等ももう30歳。音楽家として、またひとりの人間として重ねられてきた人生観を開示したものであり、人生が音楽という糸で結ばれた人間だからこその想いが乗っています。




