
1999年にアメリカ・ロードアイランド州プロビデンスにて結成。Chip King(Gt,Vo)とLee Buford(Dr, Prg)の2人で25年以上継続して活動しています。激重と評されるほどのドウーム/スラッジメタルを軸に電子音楽や実験的な要素を取り入れ、ヘヴィの未知なる領域を開拓し続ける。
また他アーティストとのコラボレーションが積極的で、Thou、Vampillia、BIG|BRAVE、OAAなどのアーティストと作品を共にしています。
本記事は単独名義で発表されたフルアルバム全8作、BIG|BRAVEのコラボ作『Leaving None But Small Birds』、Dis Figとのコラボ作『Orchards of a Futile Heaven』について書いています。
アルバム紹介
The Body(2004)

1stアルバム。全7曲約45分収録。結成から5年経ってようやくのフルアルバムの発表。長らく廃盤でしたが、2012年にAt A Loss Recordingsが再発しています。
音楽的にはスラッジメタルがベース。歪みと重みを備えたリフを中心に、スロウ/ミドルテンポで反復を基調としています。そこにチップ・キングの絶望を悟った甲高い遠吠えが重なり、聴覚と心に苦痛を与えてくる。この段階から2人編成とは思えないと重さと迫力を備えており、ヴォーカル入りの初期5iveといった趣があります。
また#3「Heart Ache, Even In Dreams」の虚をつくピアノ、#6「Failings」の4分50秒前後から入ってくるヴォーカル・サンプルなど、後に通ずる要素も本作には盛り込まれる。
BPMがやや速めで手数の多いドラムで畳みかける#2「The City Of The Magnificent Jewel」や#4「Culture Destroyer」辺りは原始的なロックの衝動があふれており、彼等にしてはむしろ異色の楽曲といえるかも。いずれにせよ早くも地獄との闇取引が成立したかのようで、デビュー作から加減という言葉は全くありません。
All the Waters of the Earth Turn to Blood (2010)

2ndアルバム。全7曲約50分収録。#1「A Body」を再生してずっと続く聖歌隊の合唱に、The Bodyを流しているはずなのに間違えた??と大半の人は思うはず。7分にも及ぶ長い前フリを経て、ちゃんとひとでなしの重低音はやってくる。
6年ぶりのフルアルバムは、スラッジメタルという安易なカテゴライズを早くもはねのける越境性を示します。13名からなる合唱団のAssembly of Light Choirを起用(ここに所属するChrissy Wolpertは、以降の作品でもたびたびゲスト参加を果たす)。さらにピアノやヴィオラ、ノイズなどを演奏するゲストメンバーを迎えた30名近い編成で制作。
スラッジを基盤にしたスタイルは変わらないものの、ダブ~インダストリアル的な音響処理、有害化された讃美歌、生々しい恐怖を煽るヴォーカル・サンプルなどを配合して重苦しさに拍車をかけています。超重量級のサウンドと人間卒業系の甲高い絶叫、ピアノが容赦なく聴き手を痛めつける#2「A Curse」はThe Bodyを端的に表したような楽曲。
”テーマ的には、人類から距離を置こうとするものには影響を受ける。人類は本質的に欠陥があり、そこから良いものは生まれないと考えているからだ“という発言がRVSのインタビューに残ります。当然のように、この人たちの頭や倫理観は大丈夫?という部分は散見される。
ユニバーサル・アンド・トライアンファント教会というカルト教のサンプリングを用いた#3「Empty Hearth」ではネイティヴのまくしたてる言葉とぶつ切りのエディット処理が印象的。またオウム真理教のサリン事件を題材にした#5「Song Of Sarin, The Brave」も収録。当時はジ〇・ジョーンズ、麻〇彰晃、チ〇ールズ・マンソンに影響を受けたと述べていたそうな。
バンドの出世作として名高い初期の名作。ちなみにPitchforkのレビューでBest New Musicにはなってないが、8.5という高いスコアを獲得しています。
Christs, Redeemers (2013)

3rdアルバム。全10曲約44分収録。Thrill Jockeyへ移籍してのリリース。前作に引き続き、合唱団のAssembly of Light Choirが参加しています。また本作から協力関係者となる男性ヴォーカリスト、Ben Eberle(Sandworm)。彼も以降に準レギュラーを張る存在。
”私は世の中のほとんどの人をあまり好きではないし、信頼もしていません。これは凶悪犯や暴力の問題というより、私たちと社会の間にある隔たりの問題です(Tiny Mix Tapeインタビューより)”と仙水忍よりも人間嫌いであることは、メンバー2人が銃を構えるジャケット写真からも見て取れる。
作風としては前作の延長上。ですが、比較するならば曲尺を短めに設定して平均4分半ほどにまとめており、焦点はより定まっている。どんよりと重苦しいノイズとチップ・キングによる周波数のおかしい絶叫を軸足に、神聖さを呼び込む女性たちの合唱やストリングスが助力し、崩壊と救いの二律背反を突き付けます。
その特徴を発揮した#2「To Attempt Openness」や#4「An Altar Or A Grave」は本作の目玉。それらの慈悲を乞うような聖歌すらThe Bodyの圧殺地獄の前に圧し潰される。不快感を増幅させるヴォーカル・サンプル、SUNN O)))ばりのドローンと正気を失う要素は出し惜しみなく。
#10「Bearer Of Bad Tidings」では予想外のブラストビートに乗っかかるノイズギター+絶叫の冒頭70秒を過ぎると、どん底のブラックホールが口を開けて待つ。”生きる苦しみに勝利はない屈辱のみ(#6)”、”この世はすべて墓場(#10)”など生への諦観に満ちた歌詞も絶望感を助長しています。
I Shall Die Here(2014)
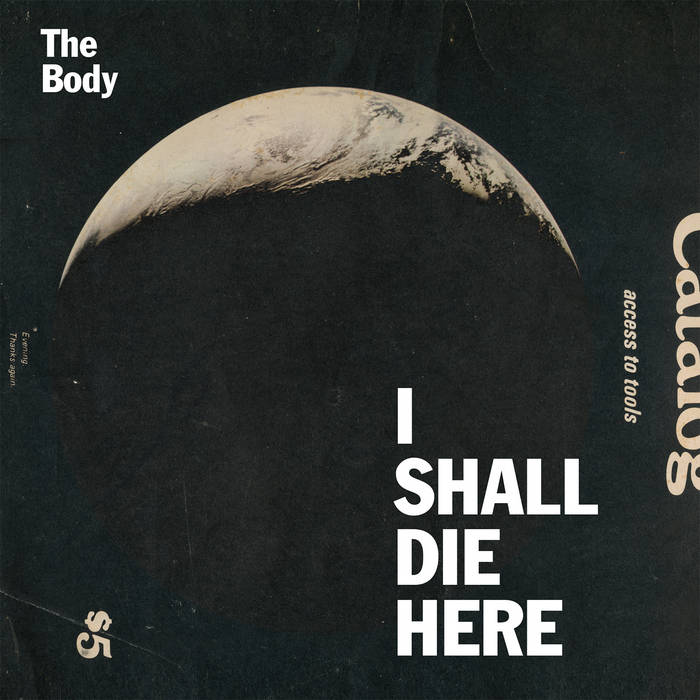
4thアルバム。全9曲約40分収録。2013年にリリースした『Excavation』で世界中から話題を集めたThe Haxan Cloakのプロデュースを受けて制作されています。
2作続けて作品に幅と豊かさをもたらしていたAssembly of Light Choirの参加はなし。代わりにエレクトロニックな要素を強めて、彼等の特徴であるスラッジメタルの重音と交配することでおぞましい呪術性を増しています。戦慄を覚える序曲#1「To Carry the Seeds of Death Within Me」から前作までとの違いを感じさせる。
作品全体を通して以前まで少なからず存在した神聖さやメランコリックな時間を排除し、白や光の入り込む余地がない闇を広げています。それは直訳ではありますが、”夜は明けない(#3)”、”闇に取り囲まれる(#6)”といった曲名からも伺える。
ホラー映画のシーンを切り取ったようなストリングスやプログラミング、Andy Stottなどに代表されるModern Love系列に連なるくぐもった音響、パーカッションがもたらす闇儀式のような雰囲気。それらが元々持っていた性質に加わり、どん底への転落幇助に活用されています。
前作に引き続き参加のBen Eberleが狂気を注入するパワーエレクトロニクス#4「Hail to Thee, Everlasting Pain」は、デュオの発展をより強調する。電子音を大幅に加えてもフィジカル的な強度が全く落としておらず、背筋が凍える恐怖感に直結させてる辺りもたちが悪い。
本作について”完全に実験的なアルバムをつくりたかった”とメンバーは発言していますが、ジワジワと嬲り殺すのも、一思いに鉄槌を打ちつけてやることも厭わない。それも定型にとらわれず、自分たちの音楽を前進させた結果。
No One Deserves Happiness(2016)
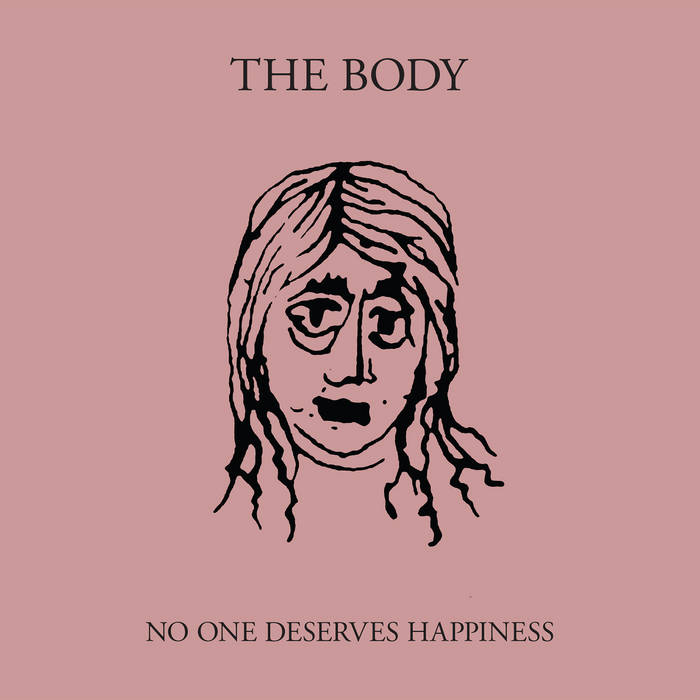
5thアルバム。全10曲約48分収録。”最も粗悪なポップ・アルバムを作ることを目指した。 絶望と孤独というアルバムのテーマは、The Bodyの特徴であるヘヴィネスと80年代のダンス・トラックという、ありそうでなかった組み合わせによってもたらされた“という記述がBandcampに載っています。
ポップという言葉に釣られて聴いちゃうと阿鼻叫喚しそうですが、彼等の作品では聴きやすい部類に属すのは確か。ほぼ全編にわたって女性ヴォーカルを導入し、#5「Two Snakes」にはビヨンセにインスパイアされたベースラインを取り入れているそう。人を遠ざける要素をコンプリートしにかかっていた前作からはえらい違いです。
ここにリズムマシンのTR-808、チェロ、トロンボーンが追従してThe Bodyの音楽は拡大されています。ポップス~R&B調の強い楽曲#2「Shelter is Illusory」や#6「Adamah」といった楽曲からは本作の特徴的な部分が表れている。
ただ、ポップや前作から引き続くエレクトロニックなエッジを持ってきても、The Bodyの絶望や重低音と合算することで得体のしれない特産物となっているのは事実。そもそもタイトルが”誰も幸せに値しない”ですし。#3「For You」なんて曲名に似つかわしくない凶悪ノイズによる苦悶が待っている。
I Have Fought Against It, but I Can’t Any Longer.(2018)

6thアルバム。全10曲約49分収録。タイトルは『灯台へ』で知られる作家のヴァージニア・ウルフの遺書から引用。本作は主に過去のレコーディングされた素材を使って再構築された作品とのこと(参照:Bandcamp)。
New Noise Magazineのインタビューでリー・ビュフォードは”私はドラムを叩かないようにしていたし、チップはギターを弾かないようにした。もっとエレクトロニックにしようと思っていたんだ“とも答えています。The Bodyの2人による生楽器の頻度は減らし、インダストリアルやヒップホップとの交配を密にしていますが、鼓膜と神経を擦り減らす重苦しいスタイルは変わりません。
前作から引き続くTR-808のマシンビートにドローンノイズ、ストリングスやホーンの演出、準レギュラーであるChrissy Wolpert (Assembly of Light Choir) とBen Eberle(Sandworm)の歌唱参加。そういった要素をまとめあげ、優美な性質と耐えがたい苦痛の両面をあぶり出しています。
#1「The Last Form of Loving」や#8「Blessed, Alone」はVampillia的な雰囲気ありますし、#3「Party Alive」は異形化したBen Frost、#7「An Urn」における絶望のエレクトリカルパレードまで多様な側面をさらけ出す。
目玉はLingua Ignotaが参加した#5「Nothing Stairs」でインダストリアルなビートを軸にホラーテイスト、ストリングスの揺らぎ、伸びやかな歌唱からデスヴォイスまでが絡んで強烈な印象を残します。ラストの#10「Ten Times a Day~」ではチェコの小説家であるボフミル・フラバルの『あまりにも騒がしい孤独』をしめやかなピアノの伴奏にのせて朗読。様式美に抗うヘヴィミュージックの価値を改めて示しています。
I’ve Seen All I Need to See(2021)

7thアルバム。全8曲約38分収録。Echoes And Dustのインタビューに”ライブのようなサウンドにしたかった。ライブでは音量とディストーションが重要になる“という発言が残ります。
以前からのコラボレーターであるChrissy WolpertoとBen Eberleの参加はありますが、ゲストでまかなっていた豊かさをディストーションによって補完。ここにきてThe Bodyたらしめるズッ友2人によるギターとドラム+遠吠えの効力を高めるスタイルとなっています。
プログラミング音や#1「A Lament」における詩の朗読は登場するも、躍動感のあるSUNN O)))という感じが基本的には続く。あくまで音源でしかないにしても、自動ドアが勝手に反応しちゃうんじゃないかと思うぐらいの圧と振動。
ここにBen Eberleのブラックメタル寄りの金切り声が乗ってくるので、余計に粗悪。#6「They Are Coming」はそれが顕著。直近2作続いたエレクトロニックな要素や優美な瞬間はほとんど排除されており、このタイミングで脳みそを真っ黒にして終末をみる作風があまりに痛快です。
#2「The City Is Shelled」や#7「The Handle/The Blade」など笑顔へのアクセスを閉ざす曲ばかり。聴いた後にメディカルチェックを受けることが推奨されます。
Leaving None But Small Birds(2021)

BIG|BRAVEとのコラボレーション作。全7曲約38分収録。共にスラッジ/ドローンを拠り所にしている2組ですが、その領域から外れてカントリーとフォークのルーツを呼び起こすアルバムを作るという課題を設定。そしてBIG|BRAVEのRobin Wattieがアパラチアやカナダ、イギリスの賛美歌やフォークソングから歌詞とメロディラインを編集したとのこと(出典:Bandcamp)。
実際にアコースティック楽器とRobin Wattieの歌声を主演に据えたフォークソング集となっており、2組が手を組むことで想像される大音量大会にはなっていません。抑制されたパーカッションや味付け程度のディストーション・ギターもさることながら、チップ・キングが叫び声を一切あげていないのも特徴。
聴いているとBIG|BRAVE寄りとの理解にはなりますが、静けさの中にも重みや緊張感といったものを巡らせることができるのは2組の培ってきた経験ゆえ。
前述した音響の穏やかな側面はありますが、児童労働と労働者の搾取を扱った#3「Hard Times」、赤ん坊を殺された女性についての#6「Polly Gosford」など取り扱っているテーマは重い。それらをRobin Wattieが犠牲者に力を取り戻すために物語を再編集。嘆くためだけではない前進の歌集として意義深い作品となっています。
Orchards of a Futile Heaven(2024)

ベルリンを拠点にするDJ/プロデューサーのDis Fig(Felicia Chen)とのコラボレーション作。全7曲約38分収録。お助け重音ツインズことThe Bodyはコラボ作の発表も活発で、相手の特徴を活かした併走で驚くような作品を生み出し続けています。
Dis Figは本作をきっかけに聴きましたが、HYPERDUB辺りを思わせる暗黒トーンのミニマルダブに彼女のエコーをかけた歌声がその音響に溶け込むもの。まどろみの中へと人を誘うかのようです。その特性をThe Bodyの無差別級スラッジが過圧倍々ゲームに拍車をかけ、世捨て人の甲高い遠吠えが人生終了の警鐘を鳴らす。
これらの組み合わせがパワーカップルとして一枚岩でぶつかってきます。ネット回線は重いと困りますが、The Bodyは重くないと困るわけで今回のコラボはきっちりと重い。さらにはインダストリアルな工業的質感も加味されています。
スピーカーが壊れているんじゃないかと思えるぐらいに歪んだ音が波及する傍ら、単純に地獄行きとはならないのはDis Figの歌やエレクトロニクスに魔性の魅力があるためでしょうか。#3「Dissent, Shame」や#5「Holy Lance」はどっしりとした重低音支配の中で官能的な揺れ動きを感じさせます。
9分超の#6「Coils of Kaa」からラスト#7「Back to the Water」ではDis Figが聖と悪の祈祷往来する中、The Bodyは拷問のヘヴィさで追従。これほど過酷な消耗戦を繰り広げていても、不思議な中毒性が存在するのが本作の肝でもあります。
”メタルとエレクトロニック・ミュージックを融合させることで、メタルとエレクトロニック・ミュージックの枠にとらわれないヘヴィ・ミュージックの新たな道を模索した(プレスリリースより)”とのですが、その越境と合成の成果が表れている。
The BodyとDis Fig。どちら側を入口に本作を手に取ったとしても、コラボ相手側の音楽の扉を開けて入っていきたくなるぐらい双方の美学が引き立っている。それほど見事なコラボ作品。
The Crying Out Of Things(2024)

8thアルバム。全9曲約36分収録。”この作品には私たちが過去に手がけたすべての作品の側面があると思う(Louder Than Warインタビューより)”。
活動から四半世紀にわたって未知なるヘヴィ道の開拓を続けてきたデュオですが、前作の並外れた歪み大音量作戦からは離れ、本作においてキャリアを網羅するような品をつくりあげてきました。スラッジメタル+ノイズの基本的作風に様々な援護射撃を加える形、それをいつになく簡潔な尺の中で実現(1曲平均4分で長くても5分半)。
ホーンの朗らかなセクション、リズミカルなビートの快活さなど意外に感じる部分はあります。だからといってバランスを重視した生温い感じはなく。ノイジーなえげつなさや荒涼とした雰囲気は相変わらずです。
コラボしたばかりのDis Figが本作にも名を連ねており、揺らぎを重視した#8「The Building」においてミステリアスな浮遊感を与えている。そして儚さと苦悶が渦巻く終曲#9「All Worries」。虚無のハーモニーがもたらすのは痛みか、哀しみか。
網羅とは先述したものの、キャリアの要約といった表現も本作にはあてはまる。とはいえ、聴き終わるとぐったりとするほど重圧的なサウンド。The Bodyは今なお脅威であることを印象付けています。ちなみに人間嫌いで知られる彼等もThe Quietusのインタビューでは終わりの見えないパレスチナへの苦境について心情を吐露している。










