
元ConstantsのWill Benoit(Vo,Gt,Ba)を中心に、ConstantsやJunius、Caspianでの実績があるメンバーが集まったバンド。2017~2018年頃に結成されて現在は4人組。前身バンドを受け継ぐオルタナティヴ・メタルやポストメタル、シューゲイザーが調和したサウンドを志向している。
本記事は2025年3月にリリースされた最新作となる3rdアルバム『Let The Light In』を含む、フルアルバム3作品について書いています。
作品紹介
The Fall(2018)

1stアルバム。全9曲約36分収録。当時は3人編成で中心人物のWill Benoit(Vo,Gt,Syn)、Caspianの現ドラマーであるJustin Forrest(Ba)、元ConstantsのDuncan Rich(Dr)が構成要員です。
そのメンバーの内訳を見てもConstantsの延長上にある音楽を思い浮かべるわけですが、いわゆるドゥームゲイズを追うどっしり感と陶酔感の2枚看板が効いています。しかしながら、Constantsの最終作『Pasiflora』ほどシューゲイザー寄りではなく、重厚で推進力を伴ったもの。
例えるなら『Conqueror』期のJesuがBPMをもう少し速くした感じというか。#2「Chemical Joy」や#3「Open Wounds」はそういった性質を受け継ぎつつ、シンセサイザーの使い方にも影響が垣間見えますしね。#6「Starless Sky」にしても鼓膜や体に圧を感じるほどの重みがあるのに、丸みを帯びた聴感。ささやくというよりかはもう少しだけ輪郭を持つヴォーカルは歪みに埋もれず、その上を漂っている。
1曲平均して4分強にまとめあげていて(5分以上の曲はない)、ダイナミクスの満ち引きも確かな技巧によるものです。ちなみにMetal Injectionでは”ドゥームポップ”と形容されたようで、これがバイオグラフィーやリリースインフォに載るぐらいのキャッチフレーズとなっています。
The Shape of Everything(2022)
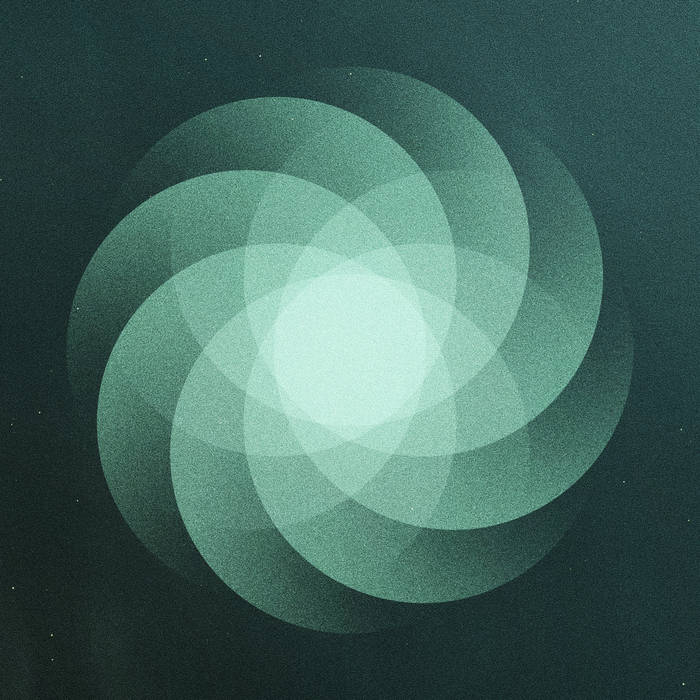
2ndアルバム。全8曲約34分収録。2021年にビリー・アイリッシュの「everything i wanted」をカバーしたことで話題になったSOMは、Pelagic Recordsへと移籍。Michael Repasch-Nieves(ex-Junius)とJoel Reynolds(ex-Constants)の2人がギターで加入しており、トリプルギター編成の5人組としての作品となります。
だからといってヘヴィに舵を切らず、甘美さとテクスチャーに重きを置いた感じに聴こえる。どっしりとしていても圧迫感が控えめな音の壁を前にして、本作ではギターがメロディックな味付けをし、シンセが広がりを与える役割へとシフト。ヴォーカルはささやきスタイルで感情を添えていくのは変わりなし。胃もたれしない重量感の調整を施した上で、淡い陶酔をもたらしています。前作に引き続いて1曲平均4分の尺でそれを実現。
アルバムの性質はオープナー#1「Moment」にてほぼ代弁されていますが、ドゥームゲイズとポストメタルとドリームポップの間を揺れ動きながら、HUMや中期のDeftones的なタッチが加味される。#6「Wrong」はWhirrを思わせるヘヴィシューゲイズを鳴らしていますし、#2「Animals」や#5「Clocks」辺りはよりメランコリックな表現が浮かび上がっています。
シューゲイズの魔法に寄った印象はあれど、取り扱い注意な重量物級のリフは健在。ただしアルバム全体の雰囲気は柔らかく淡い。そしてライトな聴きやすさがある。もっと日の目を浴びて欲しい作品です。
Let The Light In(2025)

3rdアルバム。全8曲約38分収録。引き続きPelagic Recordsからのリリース。Duncan Richが脱退して4人編成となり、Justin Forestがドラム(彼はCaspianでドラム担当)、Will Benoitがベースにスライドしている。
リリース・インフォによると1stはどん底に陥ることを味わい、前作2ndは現在進行形で暗くなり続ける世界と対峙。本作は自分自身や他人に対して慰めや活気をもたらすことを目指したという。SOMは乱暴な例えですが、デビュー時から砂糖とミルク入りのコーヒーだったわけですが、作品を重ねるごとにまろやかさとコクが引き立っているように感じます。
Deftonesを思わせる重層の中でクリーンヴォーカルが映える#1「Don’t Look Bakc」を幕開けに、圧迫と浮遊の方向転換の繰り返し。先行シングルとなった#2「Let The Light In」や#6「Nightmares」の寄せては返すポストメタル的な波動もまた心地よいものですが、ここに男性的な色艶をさらに増したWill Benoitのヴォーカルが乗っかって魅力を引き立てています。
そんな中にTorcheを思い出させるヘヴィな轟撃を挟む#5「Give Blood」も用意している。とはいえ、SOMのヘヴィネスは決して牙を向けない。歌・メロディ・ハーモニーを洗練させることで甘い陶酔をもたらしています。タイトル通りに光が差し込むような繊細なトーンと重いリフの揺さぶりが交錯する#8「The Light」は、彼等の示す希望そのもの。重厚優美なドゥームポップ、ここにあり。
私たちはどの曲も重い、暗い、奇妙、不気味など、どんな形容詞を使っても構わないと決めた。でも、そこには希望の光がなければならない。たとえそれがギターの1音だけだとしても。このアルバムは、トンネルの先にある希望の光だった。
Trebleインタビュー:WIl Benoitの発言より



